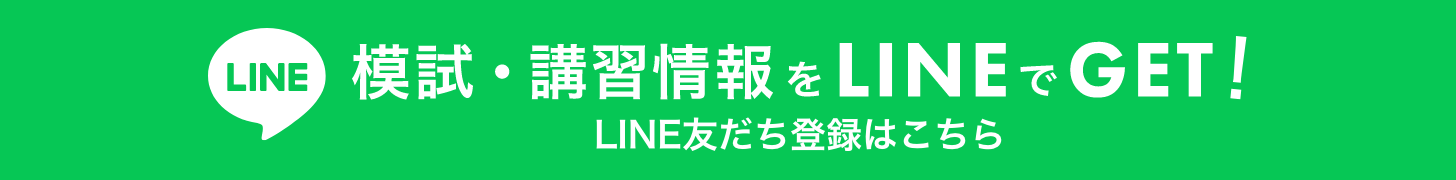大学受験の勉強に励んでいると、肩こりに悩まされることも少なくないはずです。
肩こりを抱えたまま大学受験の勉強を続けていると、受験勉強のパフォーマンス低下を引き起こす原因になりかねません。
受験勉強のパフォーマンスを向上させるためには、肩こりの原因や解消方法を知り、肩こりを解決することが大切だと言えます。
どうして肩がこるの?
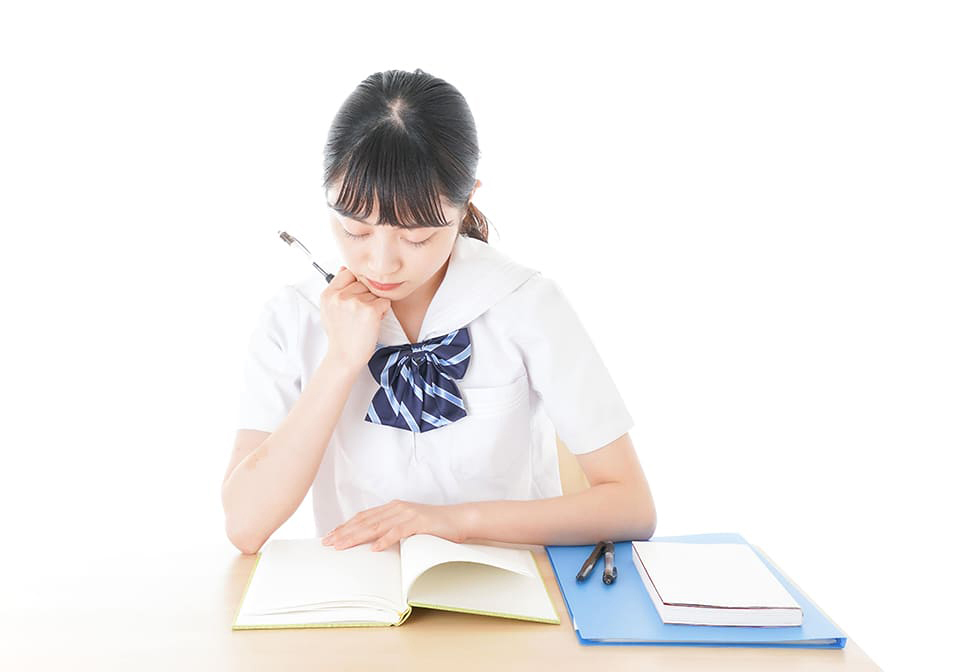
人間の頭はとても重く、首・肩の筋肉と背骨で支えられています。
肩がこる原因は、肩の筋肉の酷使によるところが大きいです。
勉強をしていると、集中するあまり長時間同じ姿勢で座っていることも多いですよね。
このように肩の筋肉の緊張状態が続くと、血流が悪くなり、筋肉がこわばることで肩こりとなります。
また、小中学生の頃からずっと同じ学習机を使っており、高さの調整を行わず机が低すぎる場合や、机の高さを考慮せず椅子を選んでしまったために、机の位置が高すぎる場合など机と椅子の高さが自身の身長に合っておらず、筋肉に負担がかかりやすい姿勢で大学受験の勉強を続けているケースがあります。
受験勉強を行うときの日頃の姿勢が原因で、無意識のうちに筋肉に負荷をかけている可能性が大いにありますので一度、机と椅子の高さが自身に合っているか確認することをおすすめします。
姿勢を正すことで肩こりを予防
肩こりは、姿勢を意識することで予防できます。
大学受験の勉強に集中して机に向かっていると、どうしても前かがみになってしまいがちです。
解答を記述している際に姿勢を正すことは難しいですが、参考書を読む等のタイミングで、背筋を伸ばしたり腕を回したりすると、肩の筋肉の緊張がほぐれ血流が良くなり、肩こりの予防になります。
正しい姿勢を意識し勉強することは、習慣になるまで煩わしいかもしれません。
しかし、ひどい肩こりは「頭痛」や「慢性的な倦怠感」を引き起こし、体調不良の原因にもなりかねないので、健康のためにも姿勢を意識することは重要です。
また、勉強の間にストレッチを取り入れると、息抜きにもなります。
ストレッチで教科と教科の間に区切りを付けると、勉強の効率も上がるかもしれませんね。
肩こり解消ストレッチをご紹介
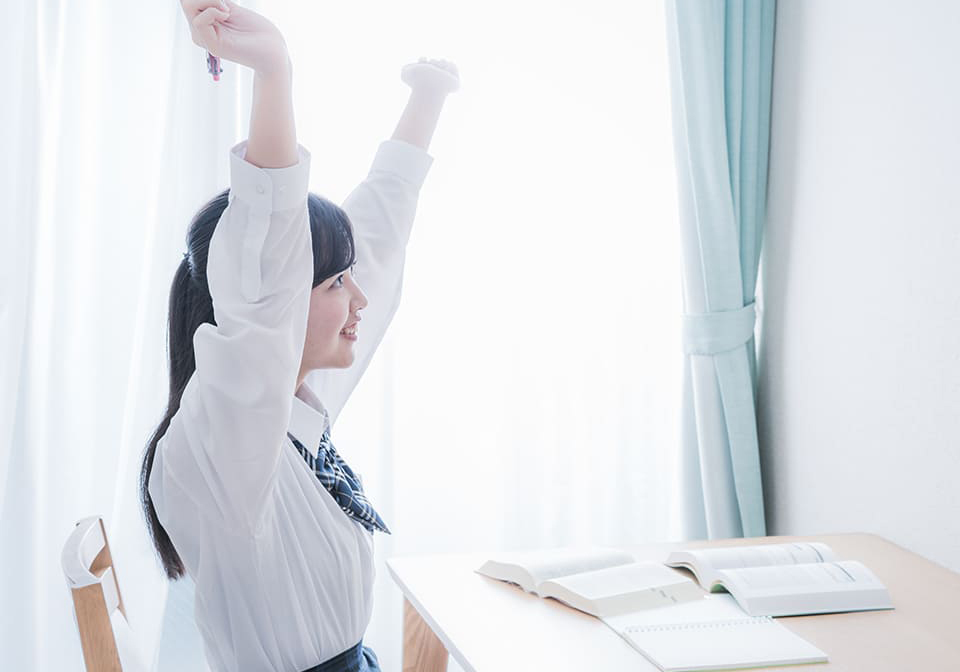
肩甲骨周りの筋肉をほぐすストレッチの方法
腕を後ろに回して軽く手を組み、胸を反らしながら肩甲骨周りの筋肉を動かしていきます。
次は腕を前に伸ばして軽く手を組み、身体を前に倒しながら肩甲骨周りの筋肉を伸ばすことで、肩甲骨の周囲の筋肉にしっかりアプローチし、凝りをほぐすことができます。
左右の肩をゆっくりと回すストレッチの方法
両手を肩の上に置いて、ゆっくりと肩を回していきます。
早く回してしまうと骨に良くないので、時間をかけて回すことが重要です。
前に5回、後ろに5回ほど回すことで血液循環が改善され、肩こりによる肩の重みを解消することができます。
特に凝っている部分がある場合は、その部分を適度な力で揉んだり叩いたりするのも簡単ですが、効果があります。
叩き方や揉み方が強すぎると筋肉を傷めてしまう恐れがあるので注意が必要です。
肩こりを解消するためには、弱すぎず強すぎない、気持ちいいと思う適度な力で行うことが大切だと知っておきましょう。
おわりに
大学受験の勉強に励んでいる人の中には、肩こりに悩まされる人は少なくないです。
知らず知らずのうちに、勉強中の姿勢の悪さによって肩こりを引き起こしている可能性があります。
姿勢を正して大学受験の勉強に励むこと、勉強の合間にストレッチを実践することをおすすめします。
これらに気をつけておくことで肩こりが解消され、勉強のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。