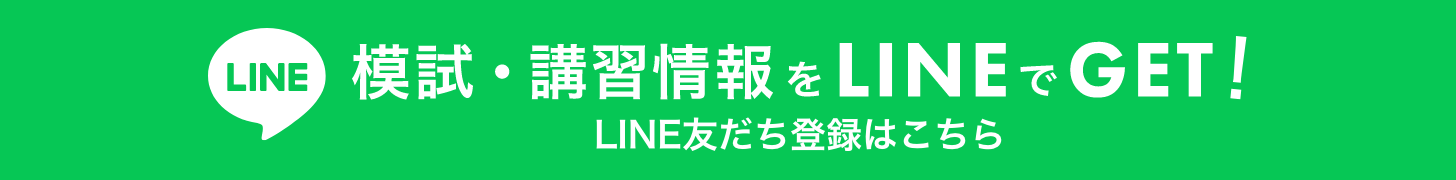デスクライトを適切に使って、勉強の効率アップ!
勉強をするときに「デスクライト」を使用している人は多いのではないでしょうか。
デスクライトで手元を明るくすると、疲労を感じにくくなり、集中力がアップするというメリットがあります。
しかし、デスクライトの使用方法を誤ると目に悪影響を及ぼして、受験勉強に支障をきたすおそれもあります。
そこで今回は、デスクライトの適切な使用方法と選び方のポイントについてお伝えします!
勉強机にぴったりなデスクライトとは…

勉強机に設置するデスクライトの選び方と、設置する時に押さえておきたいポイントを確認しましょう。
まぶしさ
目の健康を守るために、デスクライトの光が直接目に入らないようにしましょう。
また、強すぎる反射光も目の疲れや集中力低下の原因となります。
ライトの光が強く、照り返して顔に反射するようなら、デスクライトの位置を少し高くしたり、左右へずらしたりして、本やノートに反射して目に入る光の量を抑えましょう。
勉強机にデスクライトを設置するときは、机に白い光沢紙を置いて、ライトをつけた時にまぶしく感じないかを最初に確認するのがおすすめです。
影
デスクライトを設置するときは、ライトをつけた時に手元に影ができないように、位置や角度に注意しましょう。
右利きの人は左側に、左利きの人には右側にデスクライトを置くと影ができにくくなります。
勉強するときの姿勢によって影のできる位置が変わるので、光の角度を変えることができる可動式のデスクライトがおすすめです。
高さ
デスクライトの位置が低すぎると、照らす範囲が狭くなって、手元が十分に明るくならないおそれがあります。
手元が暗いままでは、教科書やノートの文字を読むときに凝視してしまい、瞬きが減って目が疲れやすくなるので注意が必要です。
手元をしっかり照らすことができるように、デスクライトは頭より高い位置に設置しましょう。
部屋全体を明るくしよう!

デスクライトを使用する際に、もう一つ注意したいのが、部屋全体の明るさです。
デスクライトで手元の明るさを確保できているからといって、部屋の照明を暗くしている人は要注意です!
人の目は、暗い場所では光を取り入れるために瞳孔が大きくなりますが、反対に明るい場所では瞳孔が小さくなります。
部屋が暗い状態でデスクライトを使用していると、手元から周囲に視線を移すたびに瞳孔を拡げたり縮めたりする動きを繰り返してしまうので、目が疲れやすくなります。
目にかかる負担を軽減して、受験勉強を効率よく進めるためには、部屋全体をしっかり明るくして、手元と部屋の明るさに大きな差ができないように心がけましょう!
明るすぎる照明はNG!
勉強部屋に適した明るさとはどのくらいなのでしょうか。
令和3年4月1日に施行された文部科学省の学校環境衛生基準によると、
『教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。
また、教室及び黒板の照度は、500lx以上であることが望ましい。』
とされています。
また、日本工業規格(JIS規格)が推奨する勉強や読書に必要な照度は、750lxとされていますので、照明の明るさは500~750lxを目安として考えると良いでしょう。
そうはいっても、照明は明るければ明るい程良いのではと考える人もいるかもしれません。
しかし、照明が明るすぎると目にかかる負担が大きくなり、疲れ目の原因にもなります。
疲れ目が悪化すると、肩や首の凝り、吐き気などを引き起こすこともありますので、目の健康と集中力を保つために、勉強机で使用する照明とデスクライトは適度な明るさのものを使用しましょう!
集中できる環境で勉強しよう!
志望校合格にむけて、集中して受験勉強ができる環境が大切です。
予備校や学校に通う時はもちろんのこと、自宅にいる時にも集中して受験勉強に打ち込めるように学習環境を整えておきましょう!
勉強の効率アップに最適な照明の種類や効果的な照明の使用方法については、『勉強の効率がアップする環境づくり-勉強部屋に最適な照明について』をぜひご参考に。
Tweet