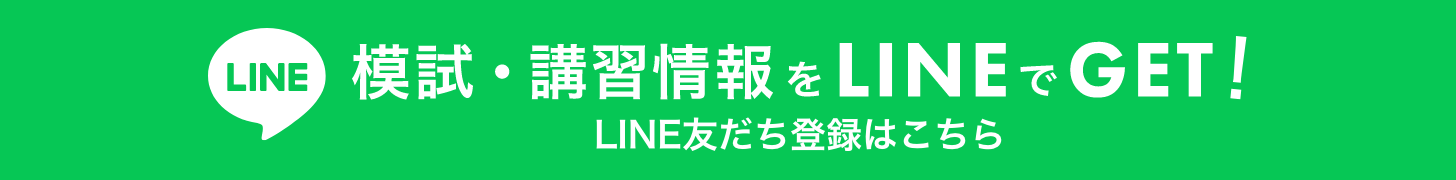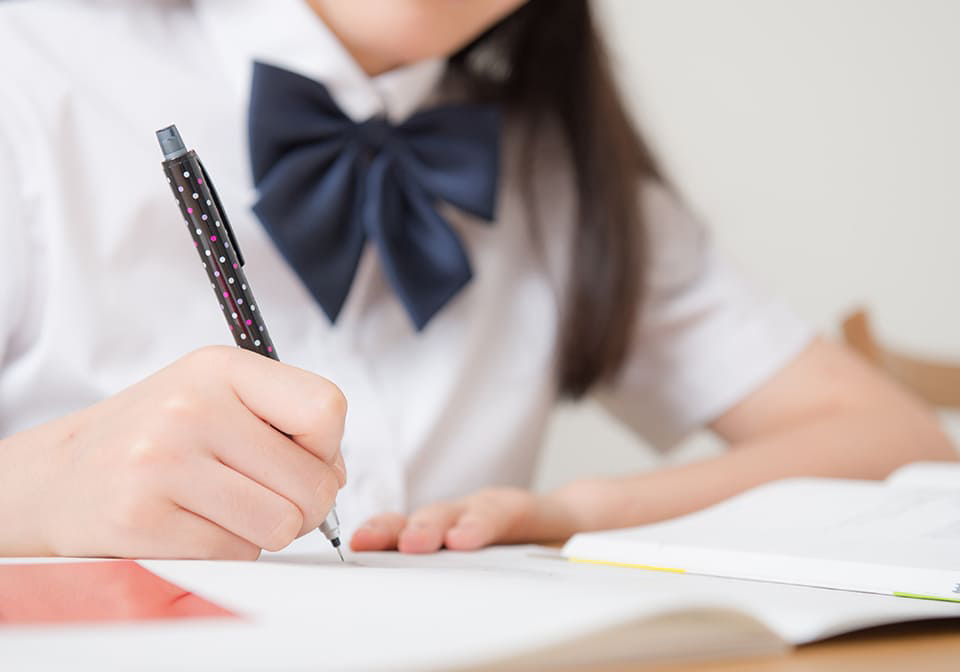受験生 vs 睡魔
「春眠暁を覚えず」という言葉はありますが、夏がもう目前なのに勉強中に眠くなってしまう…そんな経験はないでしょうか。
受験生の皆さんにとってはかなり厄介ともいえる勉強中の眠気。
今回は睡魔に打ち勝つ方法をご紹介します。
睡眠時間と眠りの質
かつては「四当五落」といって「睡眠時間が4時間の人は合格するが、5時間以上寝ている人は不合格になる」といった言葉が受験生の間に広く伝わっていました。
けれども今では反対に『4時間睡眠では認知能力が低下し、勉強の効率が悪くなる』と言われています。
受験生の平均睡眠時間は6~7時間ほどとされています。
必要な睡眠時間については、個人差もありますが、極端に睡眠時間を削ってしまうのはおすすめできません。
また、寝る前にテレビやスマートフォンを見ることも避けた方が良いでしょう。光の影響で脳が覚醒した状態では、質の良い睡眠がとれません。
“睡眠時間はきちんと確保できているのに眠い”という場合は、眠りの質を良くする必要があります。
そのためには就寝30分~1時間前には、光の刺激を受けないように心がけましょう。
簡単にできる眠気撃退法

睡眠時間も、眠りの質もきちんと気遣っているのに、眠くなってしまう…そんな時に使える眠気撃退法をご紹介します。
1. 深呼吸・空気の入れ替え
室内の二酸化炭素濃度が高いと眠気につながるといわれています。
人の多い自習室や教室で勉強しているときは、教室の外に出て深呼吸してみましょう。
根を詰めてこもりきりになっている自室も、二酸化炭素濃度が高くなりやすいため、窓やドアを開けたりして、こまめに換気をしましょう。
2. 眠気覚ましのツボを押す
イスに座った状態でも簡単に試せる、眠気覚ましに効くツボを押してみましょう。
ツボは、複数の効果を持つものも多いので、眠気覚ましだけでなく、体の不調改善にも役立ちますよ。
★手のツボ『中衝(ちゅうしょう)』は中指の爪の生え際から2~3mm下にあります。
親指と人差し指で挟んでゆっくりと押してみましょう。
眠気解消のほかに頭痛にも良く効くとされています。
★目のツボ『清明(せいめい)』は、鼻の付け根あたりの骨と、目頭の間にあります。
押すというよりは優しく引っ張る、つまむイメージで刺激するのがポイントです。
ツボ押しをしたあと、視界が晴れて明るく感じたら、正しく押せているということです。
眼精疲労にも効果があるとされているので、眠気と疲れ目を合わせて撃退しましょう!
3. 耳のマッサージをする
耳全体へのマッサージによる刺激も、眠気覚ましに効果があります。
親指の腹を使って耳を摘まみ、真下にひっぱったり、左右に広げるようにしたり、少し強めの力でマッサージしましょう。
一回あたり5秒程度、回数は2~3回を目安にするとよいでしょう。
4. 短時間の仮眠をとる
どうしても眠気がとれないときは、思い切って仮眠をとってしまうのも良いでしょう。
寝すぎ防止のためには、仮眠に入る前にコーヒーを飲むなど、カフェインを取っておくのがおすすめです。
カフェインは摂取してから、だいたい15分~20分程度で効果が出るので、仮眠を切り上げるのにちょうど良いくらいの時間に目覚めやすくなりますよ。
5. 勉強の内容や教科を変える
同じ教科や内容を長時間勉強していると、脳が疲れて眠気を感じやすくなります。そんな時は、思い切って勉強する内容や教科を変えてみましょう。例えば、理科の勉強をした後に社会に切り替えるなど、全く異なる分野を学習することで、脳の異なる部分を活用することになり、疲労を軽減し集中力も回復します。また、興味を持って取り組める内容に変えることも効果的です。自分が好きな教科や、取りかかりやすい問題から始めることで、リフレッシュ効果が期待できます。
6. ストレッチなど体を動かす
眠気を吹き飛ばすためには、軽い運動やストレッチも効果的です。椅子に座ったままできる簡単なストレッチでも良いので、定期的に体を動かす習慣をつけましょう。例えば、首や肩、腕などのストレッチを行うと、血流が良くなり、脳に新鮮な酸素が供給されやすくなります。また、立ち上がって軽く体を伸ばしたり、その場で足踏みをしたりするだけでも効果があります。一回5分程度の軽い運動を行うだけでもリフレッシュでき、集中力が戻ります。
7. 環境・場所を変える
いつも同じ場所で勉強していると、脳が慣れてしまい眠気が襲ってくることがあります。そんな時は、勉強の環境や場所を変えてみましょう。例えば、家のリビングやカフェ、自習室など、別の場所で勉強することで新鮮な刺激を受け、集中力が戻りやすくなります。音楽を軽く流すことで気分転換になる場合もあります。ただし、あまりにも騒がしい場所では逆に集中できなくなるので、静かで落ち着いた場所を選ぶと良いでしょう。
8. 眠たくならないように気を付けること
眠たくなる習慣や環境を避ける工夫も大切です。例えば、食べ過ぎや消化不良を避けるために、食事量をコントロールすることなどです。満腹になると血流が消化に集中しやすくなります。また、温かい部屋で勉強していると体温が上がり、眠気を感じやすくなるので、適度な温度に保つことが重要です。さらに、姿勢を正して座り、背筋を伸ばすことで眠気を感じにくくなります。日常生活のちょっとした工夫で、眠気を防ぐことができます。
9. 夜間に十分な睡眠をとる
勉強に集中するためには、夜間に十分な睡眠をとることが基本です。夜遅くまで無理をして勉強を続けると、翌日の集中力が低下し、結局効率が悪くなります。1日の疲れをしっかり癒すためにも、規則正しいリズムで睡眠をとりましょう。特に、睡眠の質を向上させるために、寝る前の1時間はリラックスする時間を設けると良いです。スマートフォンやテレビは避け、読書やゆったりとした音楽を聴くなどして、身体と心を落ち着かせましょう。
10. 朝型の生活習慣を身につける
朝型の生活習慣を身につけることで、日中の活動が活発になり、眠気を感じにくくなります。早寝早起きを心がけ、朝しっかりと太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされます。また、朝食をしっかり摂り、体と脳にエネルギーを供給することで、午前中から効率よく勉強を進めることができます。朝の時間を有効に使うためには、前日に予定を立てておくと良いでしょう。朝の心地よい時間をうまく活用することで、一日の始まりがスムーズになります。
11. 食生活の改善
食生活を見直すことで、眠気を防ぐことができます。バランスの良い食事を心がけ、特に朝食を抜かないようにしましょう。朝食は脳のエネルギー源となるため、集中力を高める上で非常に重要です。また、間食にはナッツやフルーツなどの健康的なものを選びましょう。これにより、血糖値の急激な変動を防ぎ、安定した集中力を保つことができます。さらに、水分補給も大切です。適度な水分を摂ることで、体調を整え、脳の働きをサポートします。
眠気に負けずに頑張ろう!

今回は、眠気対策についてお伝えしました。 以前のコラムでも『受験勉強と睡眠時間の関係について』ご紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。
皆さんが眠気に打ち勝ち、受験勉強に集中できるよう祈っています!
Tweet