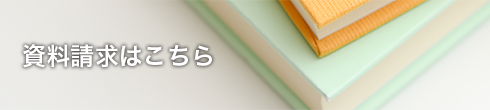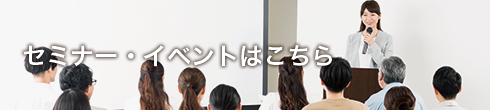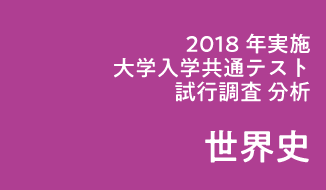2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析(国語)
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析
(英語筆記・リスニング)
2018.11.28
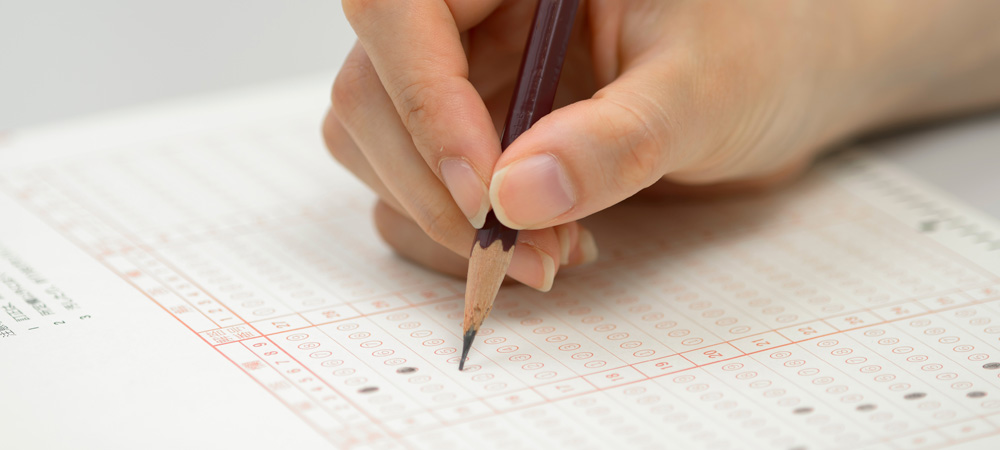
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査で出題された問題について、各科目ごと、出題における特徴的な点、設問ごとの分析などを公開しています。
プレテスト分析 英語筆記(リーディング)
試験概要
| 配点 | 100点 |
|---|---|
| 試験時間 | 80分 |
出題における特徴的な点(2017年実施の試行調査との比較)
前回の試行調査と同様に、様々な題材を用いて読解力を測定することに特化した問題となっている。
学校内における日々の活動で英語を用いることを想定して、ウェブ上に掲載された料理のレシピや交換留学生が書いた日記(ブログ)、ディベートやプレゼンテーションを行うための参考資料という位置づけの文章が題材となっている。
本文と設問選択肢の語数を合わせた総語数は約5100語で、前回試行調査とほぼ同じ分量である。
物語の概要を把握させる問題が第5問で出題された(前回試行調査では第6問)。
前回試行調査の第5問で出題されたような、文章・パラグラフの主題を把握させる問題は第6問で出題されている。
配点は1問2~3点のものが多く、一部の問題で4~5点のものもある。CEFR※のA1・A2レベルで作問された第1問~第3問の合計点が40点、B1レベルの第4問~第6問が60点という点数配分である。
- ※外国語の習熟度を評価する国際指標。
第1問 読解問題(情報検索)
文書はA・Bの2種類あり、Aは交換留学生のお別れ会に関する伝言メモ、Bは姉妹都市の交流イベントの告知記事が題材。
小問数はAが2問、Bが3問。
現行のセンター試験(英語筆記)第4問Bに近い形式で、設問の解答に必要な情報を文書の中から検索することが求められている。また、Bでは告知記事の目的を考えさせる問題も出題されている。
第2問 読解問題(テクストに基づく推測・事実と意見の区別)
Aはインターネット上に掲載された料理レシピが、Bは学校で生徒が携帯電話を使用することの是非に関する文章が題材。
小問数はA・B共に5問ずつ。
シンプルな内容一致問題は出題されず、英文の概要や要点を把握することや、文書中の事実と意見を整理・区別することが主として求められている。
前回の試行調査では「個人の意見ではなく、事実として正しいものを選べ」という問題が出題されたが、今回は「事実」と「意見」選ばせる問題が別々に出題されている(A-問4、問5)。
また、テーマについて賛否の意見を選ばせる問題でも、文中で事実として述べられている内容の選択肢がダミーとして含まれている(B-問2、問3)。
第3問 読解問題(ストーリー性のある文章の概要把握)
Aは学園祭についてのブログ、Bは異文化体験に関するコラムで、共にストーリー性のある文章が題材。
小問数はAが2問、Bが3問。
設問傾向は現行センター試験(英語筆記)の第5問に近く、ストーリーの概要・話の展開を理解する力や本文と設問選択肢の内容を照合する力が求められている。
また、Aではイラストを参照して解答する問題が出題されている(問2)。
第4問 読解問題(2つの視点から書かれた文章の比較)
生徒の読書習慣について、2人の人物がそれぞれの視点から書いた記事が題材。
小問数は5問。
2つの記事でそれぞれ述べられていることを総合したり、どちらでも言及されていないことを把握したりすることが求められており、グラフを参照する問題もある。
また、当てはまる選択肢を全て選択させる問題も出題されている(問3)。前回の試行調査のように、2人の人物の見解の共通点と相違点を把握させる傾向は弱まった。
第5問 読解問題(物語の概要把握)
アメリカのジャーナリズムにおける偉人についての物語が題材で、物語の概略をまとめたポスターの中の空欄を埋める形式の出題。
小問数は4問。
前回試行調査の第6問でも物語の概要を把握させる出題があったが、今回の問題の方が分量は少ない
(本文の総語数は約600語。前回は約900語)。当てはまる選択肢を全て選択させる問題が出題されている(問2、問4)。
解答として参照する箇所・選択肢の内容が重複していると思われる問題がある(問2、問4)。
第6問 読解問題(文章の要旨・論理展開の把握)
Aはアジアの女性パイロットに関する記事、Bはアメリカの国立公園で起こった出来事に関する記事が題材。
小問数はA・B共に4問ずつ。
前回試行調査の第5問に類似した問題だが、前回はあった文補充やバラグラフごとに見出しを選択させる問題は出題されなかった。
その一方で、文章中で述べられている情報と一致するグラフを選択させる問題が新たに出題された。俯瞰的・論理的に英文を読んで、文章・パラグラフの要旨や論理展開を把握することが求められている。
対策としてどのような学習が効果的か
単純計算で大問1つあたり約13分しかかけられないため、1つ1つの設問に時間をかけずに解いていく処理能力が必要である。
さらに、後半(第4問~第6問)のは読解量も語彙レベルも高くなるので、途中で息切れしない集中力と忍耐力が求められている。
従来のセンター試験で問われていた文法・構文の知識と理解を土台として、日々の学習で英文に触れる量=読解量をどれだけ確保できるかがカギとなるだろう。
プレテスト分析 英語リスニング
試験概要
| 配点 | 100点 |
|---|---|
| 試験時間 | 30分 |
出題における特徴的な点(2017年実施の試行調査との比較)
問題によって音声が2回流れる場合と1回だけ流れる場合がある。
音声が流れる回数は問題冊子に記載されている。A1・A2レベルで作問された問題は第4問Aをのぞいて音声が2回流れるのに対し、B1レベルの問題(第4問B~第6問)の音声は1回しか流れない。
第4問Aは前回のグラフの穴埋め問題から、イラストの並べ替え問題に変わった。
第6問Bは前回は[放送→解答→放送→解答]という流れだったが、今回は[放送→解答]という流れになった。
配点は1問3~4点。CEFR※のA1・A2レベルで作問された第1問~第4問Aの合計点が60点、B1レベルの第4問B~第6問が40点という点数配分である。
- ※外国語の習熟度を評価する国際指標。
第1問 (短い発話の聞き取り)
Aは短い発話の内容に合う英文を選ぶ問題、Bは短い発話の内容に合うイラストを選ぶ問題。
Aが4問、Bが3問。
音声は2回流れる。
英語の音声が聞き取れるだけでなく、発話の内容を理解して正答するには文法・語法の知識が重要である。
第2問 (短い対話の聞き取り)
短い対話とその対話についての問いを聞き、問いの答えとして適切なイラストを選ぶ問題が4問。
音声は2回流れる。
現行のセンター試験のリスニングでも第1問で同様の問題が出題されている。
ただし、センター試験の方は問いが問題冊子に記載されており、音声として流されない。
第3問 (短い対話の聞き取り)
短い対話を聞き、問いの答えとして適切なものを選ぶ問題が4問。第2問とは異なり問いは問題冊子に記載されている。
また、対話の場面についても日本語で問題冊子に記載されている。音声は2回流れる。
現行のセンター試験のリスニングでも第3問で同様の問題が出題されている。
ただし、センター試験では対話の場面は問題冊子に記載されていない。問4は「2人の見解が一致していることは何か」という問いが出題されている。
第4問 A (モノローグ・説明の聞き取り)
身近に起きたエピソードを聞いて、その話の内容を表したイラストを聞こえた順番に並べる問題が1問と、表を完成させるのに必要な説明を聞き取る問題が1問。
音声は1回しか流れない。
表を完成させる問題では、同じ選択肢を2回以上選ぶことができる。
1回しか流れないので、聞き漏らしがないようメモを取りながら聞くことが重要である。
聞こえた順番に並べればよい問1は取り組みやすい一方で、問2はツアーの値段のつけ方について細かい情報を注意して聞き取らなければならない。
第4問 B (複数の情報の比較)
学生寮に関する4人の話者の説明を聞き、問題冊子に記載された条件に最も合う学生寮を1名選ぶ問題の1問のみ。
音声は1回しか流れない。
音声はおそらく日本語を母語とする話者が起用されていると思われる。
各話者の説明を聞きながら、問題冊子に記載されたメモ欄を埋めることが重要である。
第5問 (講義の聞き取り)
大学での講義を聞いて、講義の概要をまとめたワークシートの空欄を埋めたり、講義の要旨として適切な英文を選ぶ問題。
音声が流れる前に問題冊子に記載された状況と設問に目を通す時間が約1分間与えられ、[講義のリスニング→3つの小問に解答→講義のリスニング→1つの小問に解答]という流れで解答する。
最後の小問では、前の講義の内容と与えられたグラフの情報とを総合して考えることが求められている。
音声は1回しか流れない。
ワークシートの空欄に埋める情報を聞き漏らさないようメモを取ることが重要である。
講義のテーマは最近よく見聞きする社会的な話題(「技術革新が人間の労働に与える影響」)である。
第6問 (対話・意見の聞き取り)
Aは2人の対話を聞いて、それぞれの話者の意見の要点を選ぶ問題が2問、Bはあるテーマについて4人の話者の意見を聞いて、反対意見を述べている人をすべて選ぶ問題が1問と、別の話者の意見を聞いて、その意見に合う図表を選ぶ問題が1問。
音声は1回しか流れない。
A、B共に意見の要旨を大まかに把握して、話者がそれぞれどのような立場を取っているかを考えることが重要である。
対策としてどのような学習が効果的か
リスニング力の向上には、毎日15~20分程度の時間をかけて少しずつ英文を聴く訓練をすることが非常に重要である。
まずは短い会話文から始めて、スピードに慣れてきたら長めのモノローグを聴くようにするとよい。また、放送内容のスクリプトを音読することも有効である。