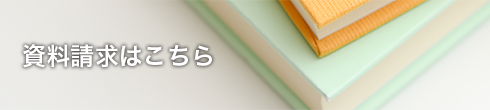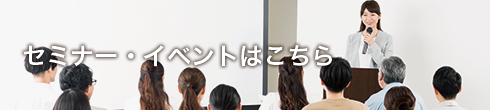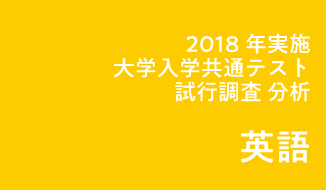2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析(英語筆記・リスニング)
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析
(世界史)
2018.11.28
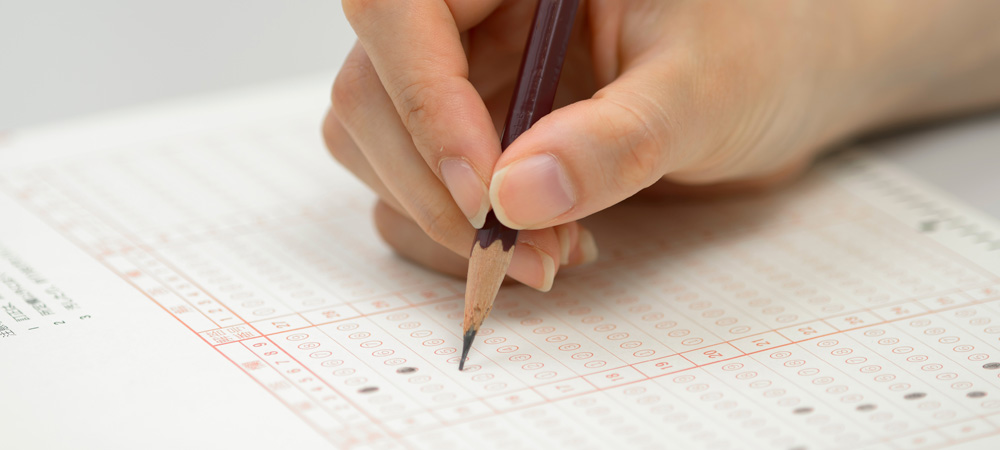
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査で出題された問題について、各科目ごと、出題における特徴的な点、設問ごとの分析などを公開しています。
プレテスト分析 世界史
試験概要
| 配点 | 100点 |
|---|---|
| 試験時間 | 60分 |
出題における特徴的な点(2017年度実施の試行調査との比較)
問われている知識の内容が、用語それ自体よりも、年代や背景の理解にシフトしている。
結果的に、昨年度の試行調査や既存のセンター試験よりも用語の難易度は下がったが、年代暗記の重要性は増した。出題形式は昨年度に引き続いて多様で、解答が連動する問題も出題された。
一方、正解を2つ選ばせる問題は消滅した。歴史史料の数はほぼ同じ、図版(絵画・写真)の数は減少したが、統計データ(表・グラフ)の数は大きく増加した。
前回にあった系図の問題は、今回はなかった。歴史史料や地図は一見すると読解が必要なように見えて、実は読解が不要な問題が多い。
第1問 (世界史における接触と交流)
Aは地中海一帯の人の移動を示した図を用いた問題。
Bは2枚の歴史上の地図を掲載し、それを説明するリード文。
Cはカナダの二言語政策についてのグラフを掲載し、生徒の調べ学習の形式に沿って問題が置かれている。
グラフは世界史では紹介されないが、地理等ではよく見るグラフなので、生徒にとって初見のものではない可能性がある。
第2問 (世界史上の政治思想)
Aはポリュビオスの『歴史』を引用したリード文で、これに関連する問題。全て知識問題で読解要素はほぼ無い。
Bは宮崎滔天の回想録を引用して、19世紀末のアジアに関連する問題を出題。
やや古い日本語の史料文ではあるが、落ち着いて読めば解答できる。難しい知識が問われているわけではない。問4は史料文中の空欄に当てはまる国名の組合せを選ぶ問題。
「康有為」等から年代を、「フィリピン」「自主独立」の語からフィリピン=アメリカ戦争の話題ということに気づけば解答できる。問6は宮崎滔天の思想として正しいものを選ぶ問題。
当然、宮崎滔天は世界史受験生にとって全く見知らぬ人物だが、問4で導いた年代と基礎的な知識で正解を導くことが可能。
ただの知識問題であることに気づけば解答は容易だが、恐れず着手できるかが肝。Cはインドネシア史に関する問題。
第3問 (世界史上のモノ)
Aはトプカプ宮殿所蔵の陶磁器の図版2点に関する問題。
問2は明代の社会・経済についての理解を問うもの。
問3は生活革命についての問題。Bは南アジアの金貨の図版とその説明文を用いた問題。
問6は発行年代の並び替え。
第4問 (世界史上の国家間の関係)
Aはポーランド分割についての絵画図版とその説明文に関する問題。
問2は連動式の問題で、(1)で図版に登場する人物を選び、(2)はその人物に関する出来事の時系列整序問題。正解が2つあり、どちらを解答してもよい。
Bは遊牧民に関する史料文を読んで答える問題。
問3は史料文の読解が問われているが、解答は容易。
問5は中国と周辺諸国についての史料文4つから、中国に臣従する立場を示したものを選ぶ問題。
史料そのものが選択肢になっている問題は、世界史では珍しい。
第5問 (世界史に関わる経済・統計)
Aはイギリスの綿工業についての授業という設定で、関連する統計データ(表・グラフ)が示され、それに関連する事項が問われた。
問2・問3はグラフの読解が必要になる問題。
特に問3の誤文選択問題は、グラフを読み飛ばすと正解の選択肢も正文に見えるところがポイント。Bは20世紀後半の米ドルに対する日本円の為替相場のグラフと、国際原油価格の推移を示したグラフに関する問題。
対策としてどのような学習が効果的か
基本的に既存のセンター試験対策から大きく変わらないが、「出題における特徴的な点」に書いたように、年代や背景に重点を置いた暗記に努めるとよい。
今回の試行調査はセンター試験よりも用語のレベルが易しかったが、本番ではどうなるかわからないので、気を抜かずに、従来のセンターレベルの用語は押さえておきたい。
センター試験の過去問演習も無駄ではない。出題傾向がやや異なるものの、十分な学習効果があるだろう。
本番でもほとんどの受験生にとって初見となる資料(史料文・図版・統計データ)が多く出題されることが予想される。
出題されそうな資料を予測して読んでおくというのはまず不可能なので、慌てないように、まずは頻出の資料に親しんでおこう。
センター試験でも2016年度以降はグラフの問題が出題されているので、これらは重点的に見ておいた方がよい。