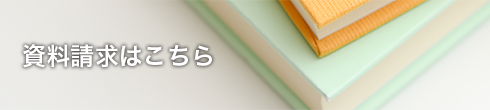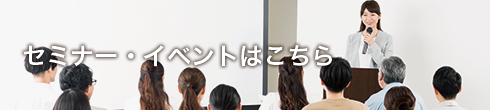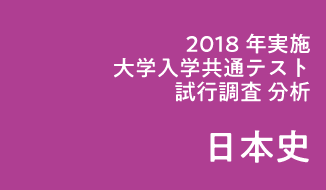2017年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析(社会)
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査(プレテスト)分析
(地理)
2018.11.28
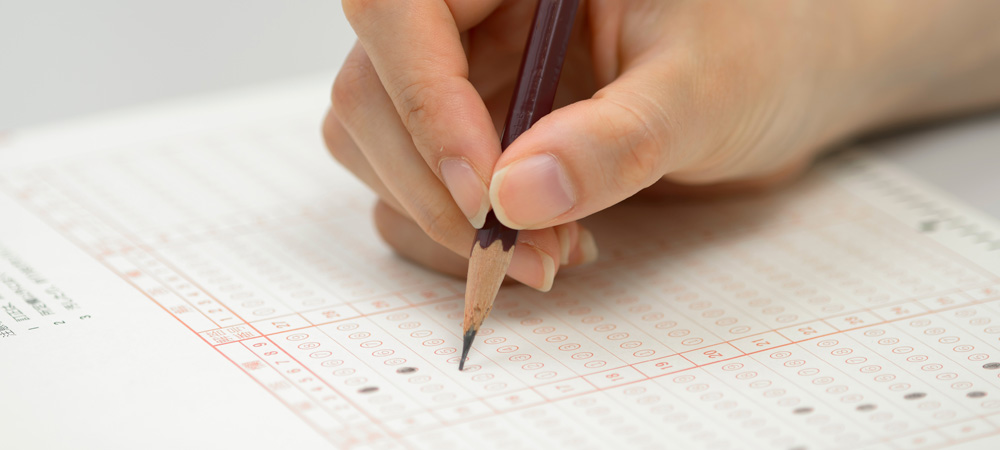
2018年度実施「大学入学共通テスト」試行調査で出題された問題について、各科目ごと、出題における特徴的な点、設問ごとの分析などを公開しています。
プレテスト分析 地理
試験概要
| 配点 | 100点 |
|---|---|
| 試験時間 | 60分 |
出題における特徴的な点(2017年度実施の試行調査との比較)
大問数は5問で変化せず、小問数は30問から32問に増加した。
前回の試行調査と同じく、大問の構成は系統地理3問、地誌1問、地域調査1問。
資料や図表の減少により、実質ページ数は6ページ減少した。
前回の試行調査と同じく、8択問題、9択問題が出題された。
前回の試行調査で見られた「すべて選べ」という出題はなくなり、代わりに「二つ選べ」という出題が見られた。
前回の試行調査と同じく、高校生の学習成果の発表という形式の大問や、仮説を立てるもとになった資料の選択など、主体的な学びを意識した出題が見られる。
難易度は大きな変化はない。
第1問 (世界の自然特性)
世界の自然特性を様々な角度から考えるための問いとあり、多様な図が使われているが、各小問は従来のセンター試験と内容、難易度ともに変化はない。
問1はGISで作成した地図や3D化した地形景観の図が使われているが、図の読み取りは容易。問2はプレート境界や火山フロントの位置を知っていれば解答可能。Bの日本周辺から考えるとよい。
問3は降水量から南アメリカ大陸の3地点における気候の形成要因の正誤を8択で判断する問題。単なる雨温図と都市の組合せの問題ではなく、気候の形成要因を深く理解しておく必要がありやや難しい。
問4は自然環境の特徴について検討する適切な方法を選ぶ問題で、問題文中の「例年に比べて」「世界の様々な地点」「客観的に」などを読み飛ばすと間違える可能性がある。
問5は堆積平野における土地利用に関する基礎的な知識で解ける平易な問題である。
問6はデータそのものは見慣れないが、各大陸の経済規模や人口から被害額や被災者数を推定する。
第2問 (資源・エネルギー・工業)
資源・エネルギーの開発と工業の発展に関する模式図から派生させた各小問を解く大問で、資源やそれを利用する工業、工業化に伴う環境問題などを総合的に問うている。
問1は各大陸の資源分布を覚えておくとともに、可採年数からどの資源の利用が多いかを判断する必要があり、やや難しい。
問2は石油と鉄鉱石の産出、加工、利用・消費の過程に関する正誤問題である。原油の輸入量に関する知識はやや高度だが、消去法で解答可能である。なお、原油の輸入量は1位アメリカ合衆国、2位中国、3位インド、4位日本、5位韓国となっている(2015年)。
問3は鉄鋼業が原料指向型の工業であることを前提に、様々な条件を考慮し製鉄所の立地の変化を考える必要がある。問題自体は平易だが、問題文や条件を整理するのに時間を要すると思われる。
問4は東アジア・東南アジアの工業に関する知識問題である。
問5はバイオマスの発電量の統計は見慣れないかもしれないが、水力と地熱は容易に判定できるため平易な問題である。
問6は3つの指標を読み取り各文の妥当性を判断する必要があり、慎重に検討する必要がある。図中の世界平均を示す点線にも注目したい。
第3問 (生活文化)
高校生が学習の成果を発表するという形式で、生活文化に関して問うている大問である。
各小問は従来のセンター試験から大きく変化したわけではない。
大学入試センターが公表している「問題のねらい」によると「多面的・多角的に探究し、考察できるように工夫した」とあり、2017年度試行調査の第2問のように、新しい教育課程を意識した大問といえる。問1はキリスト教のカトリックよりもイスラームを信仰する人口の方が多いことに注意すれば容易な問題である。問2は容易な知識問題であるが、展示資料Ⅰを参照すれば知識がなくても解答できる。
問3は雨温図の読み取りは容易であるため、そこからどのような伝統的衣服、伝統的家屋が発達したか推察する。
問4は問3で判定した気候を踏まえて、選択肢の妥当性を判断する。
問5はトウモロコシの原産地と伝播経路というやや高度な知識が必要となる。
問6は文脈を理解すれば解答は容易である。
第4問 (オセアニア)
オセアニアに関する地誌の大問で、ほぼ従来のセンター試験と同様の形式、内容である。
問1はケッペンの気候区分に関する問題で平易である。
問2はサンゴ礁の分布とその要因に関する9択問題である。問題文の「二つ選べ」を読み落とさないように注意したい。なお、Cは裾礁、堡礁、環礁のすべてに当てはまる。
問3は写真をよく見て文脈から該当する語を選べばよい。
問4は各太平洋島嶼国のODAは旧宗主国、旧施政権国からのものが多いと考えれば容易である。
問5は表の読み取りは容易であり、読み取った内容に適合するものを選べばよい。
問6は8択の中から適当でないものを二つ選ぶ問題で、解答は容易である。
第5問 (地域調査)
大分市と別府市を中心とした地域調査であり、2017年度試行調査と同じく、地理院地図が使用された。また、2017年度試行調査の第4問の問6と同じく、問いに対する仮説についての出題があった。
問1は地理院地図の読み取りで、等高線から地形を読み取ればよい。
問2は1930年の地形図と2018年の地理院地図の比較であり、選択肢を慎重に検証すればよい。
問3は図3は人数、図4は割合であることに注意したい。選択肢を一つずつ検証するのにやや時間がかかる。
問4は保育所不足という現代日本の課題について、考えられる仮説のもとになった資料を選択する問題で、階級区分図、折れ線グラフ、メッシュマップが使用されている。
問5は第二次世界大戦以後の日本経済の知識があれば容易である。
問6は文脈が理解できれば容易である。
対策としてどのような学習が効果的か
難易度や形式は従来のセンター試験と大きな変化はないが、センター試験よりも資料や図表の数が増え、読み取りにも時間を要する問題が多いため素早く解答を導く力が必要である。
そのために教科書レベルの知識を習得するのはもちろんのこと、センター試験の過去問をはじめとした多様な問題に触れて、知識を定着させるとともに資料の読解力や図表から解答に必要な情報を見抜き整理する分析力、思考力を身につけよう。