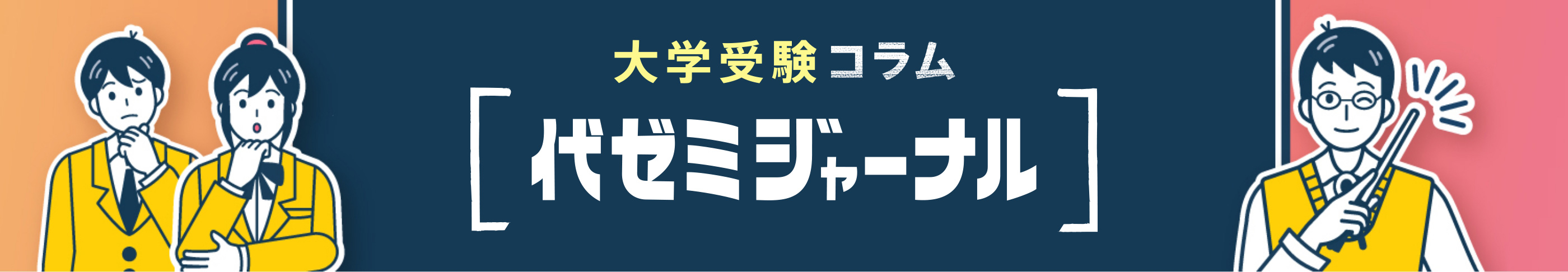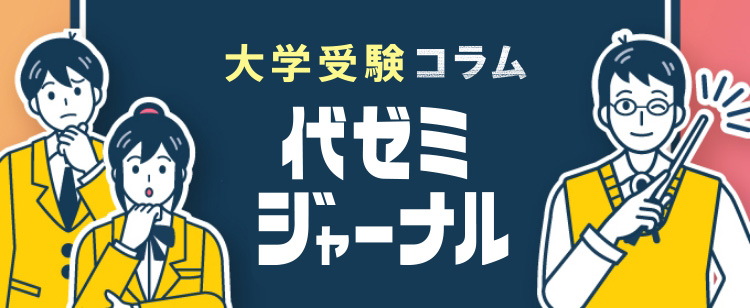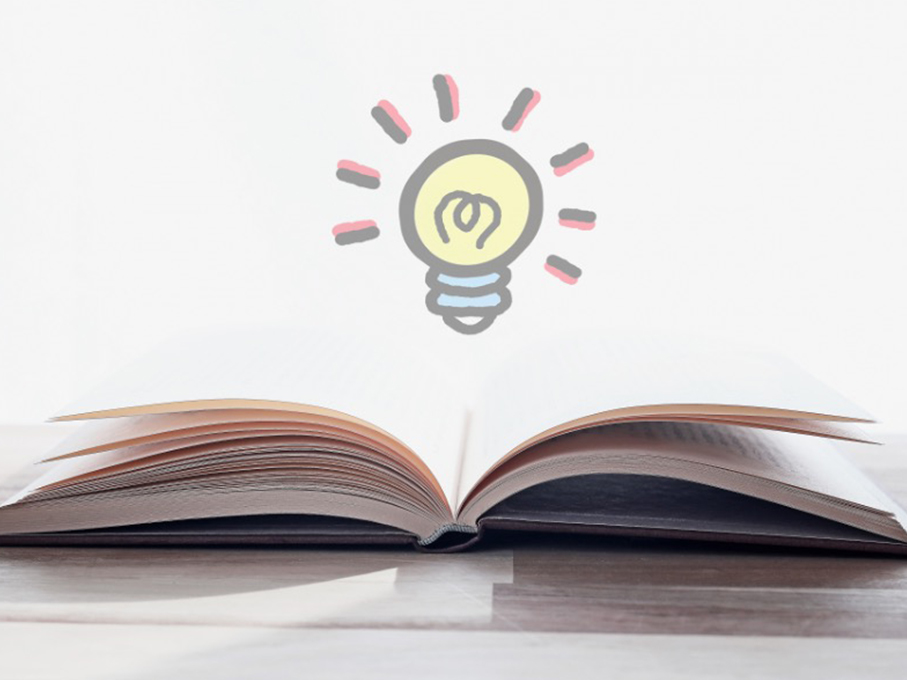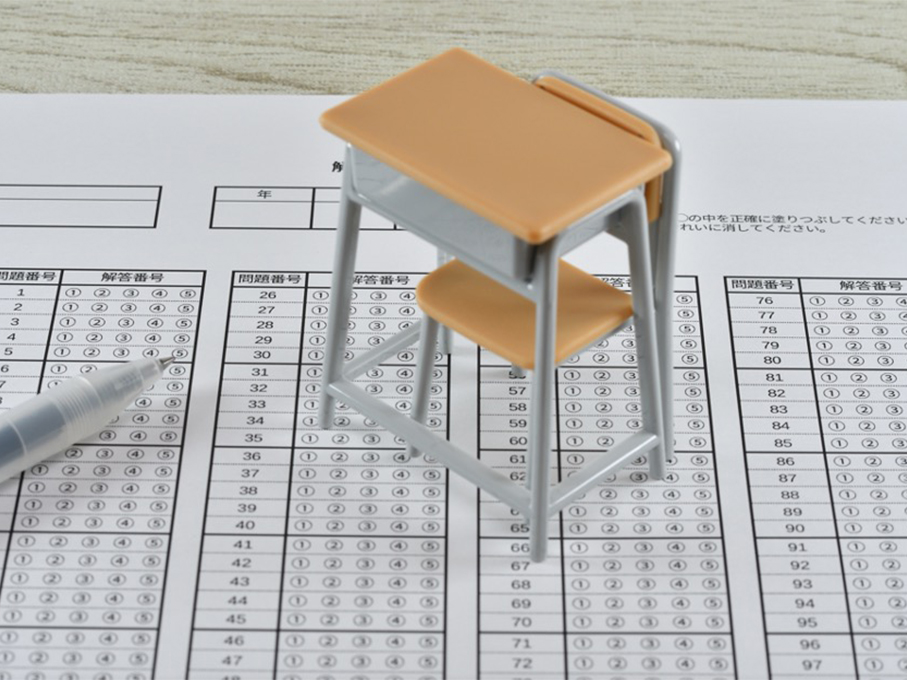代ゼミの先生から、みなさんへのメッセージ。第2回は、「英語」を担当する富田一彦先生に話を聞きました。受験勉強に向かう心構えや、英語を学ぶうえで必要なことなどを熱く語っていただきました。
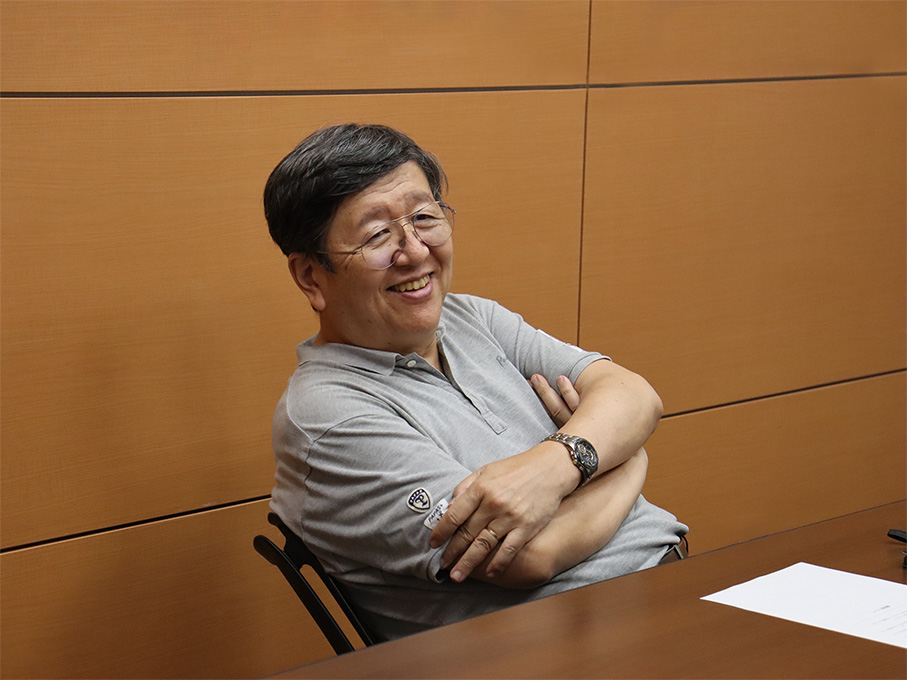
Contents
「教え方の本質は変わらない。必要なときにすぐに使える英語を教えたい」
代ゼミの講師になったきっかけは?
高校の英語教師になった3年後に、周囲に背中を押されたのがきっかけです。それから30年以上にわたり、講師の仕事を続けています。
大学生の頃は、教える仕事に就くとは思わなかったですね。高校で教えているとき、誰でも英語を理解できるようにするにはどうすればいいのかといろいろ工夫して、今の教え方になりました。本質は変わっていません。生徒が社会人になっても、思い出して使える英語を教えています。
英語を教える上で、大事にしていることは?
常に大事にしているのは、必然性と再現性です。他の教科であれば、授業で扱った問題が試験で的中することもありますが、英語は違います。教科書やテキストに載っていた文章が、そのまま本番の試験で出るということはまずありません。つまり、ここにある文章から、未知の文章をどう読むかを教えなければならないのです。
私が授業をする上で考えているのは、「他の文章を読むために、この話をする必要があるか」「この話をしておけば、別の文章を読むときに再現できるか」。これはずっと意識しています。
富田先生の授業のよさや特長を教えてください。
英語の基本的なシステムを理解できるように教えます。
勉強というのは、自転車の練習と一緒です。最初は補助輪を付けて練習して、乗れるようになると、30年ぶりでもすぐに乗り方を思い出すでしょう。これが技能の習得です。つまり「練習してできるようになり、それから時間が経っても再びできる」ということ。
でも英語は、せっかく学校で勉強したのに、大人になったら英文を読めないことに気づく人が多いでしょう。私は、自転車のように、時間が経っても必要になったらすぐに使える英語を教えたい。卒業した生徒が、いつか仕事で英語を使う場面に遭遇したときに、「あ、これ代ゼミでやったよな」と思い出せるような授業にしたいと思っています。

「自分で決めたことをやればいい。やると決めたら全力を尽くしてほしい」
生徒には、どのように教えていますか?
私の授業は、限られた時間で大学に合格するための英語力を養成することと、英語という技能の習得の両方をめざしています。そのために、1学期に基礎固めをして、2学期は受験対策中心の授業となります。
1学期は英語の基礎をみっちり教えるので、ひとつの文を読むのに1時間かかることもあります。文章全体のなかで、一つひとつの言葉のポジションや意味を正しく理解し、他の文章でどう使うかを丁寧に教えます。
2学期になると、一気にスピードアップして、とにかく問題を解きます。大学受験に合格するための勉強なので、さまざまな応用問題を解いて、再現性を高めます。
実際の授業の様子はこちら
代ゼミの魅力は何ですか?
他の予備校に比べると、代ゼミは生徒の意志を尊重するというところが大きいと思います。
私は最初の授業で、「自分で決断し、やると決めたら全力を尽くしなさい」と話します。
勉強する気がない生徒まで、手取り足取りフォローするようなことはしません。なぜなら人間は、正しい判断ができてもできなくても、常に何かを選択しながら生きていかなくてはならないからです。その人自身が決めたことなら周りが口を出す必要はないと考えています。
自分が何をするかは、自分で決めてほしい。自ら学ぼうという意志をもっている人には、代ゼミはいい場だと思います。

最後に、受験生のみなさんにメッセージをお願いします。
どんなことも、選択する前に正しいかどうかを知ることはできません。迷っていると時間ばかり経って、選ぶこと自体ができなくなります。だから、自分なりに一生懸命考えて選ぶしかないのです。
自分の選択が正しいかどうかは、結果が出て初めてわかるのですが、結果がいつ出るのかはわかりません。試験に落ちたからダメだった、受かったからよかったというのは目先の話です。自分の能力より高いレベルの大学に受かったら嬉しいかもしれませんが、いざ入学すると、周りについていけずに進級できない可能性もあります。
その逆もあって、第一志望の大学には落ちたけれど、充実した大学生活を過ごして、卒業後に仕事で活躍する人もいます。進学してどうなるかは、誰にもわかりません。「受からなかったら人生おしまい」などということはないのです。
勉強は、自分自身の適性を見極めるためにする努力です。まずはやってみて、その先どうするかは結果が出てから考えればいい。もし向いていなかったら別の世界に進めばいいのです。それは決して「負け」ではありません。
ただし、やると決めた以上は、全力を尽くしてほしい。そのための、みなさんの挑戦に必要な技術をしっかり教えます。