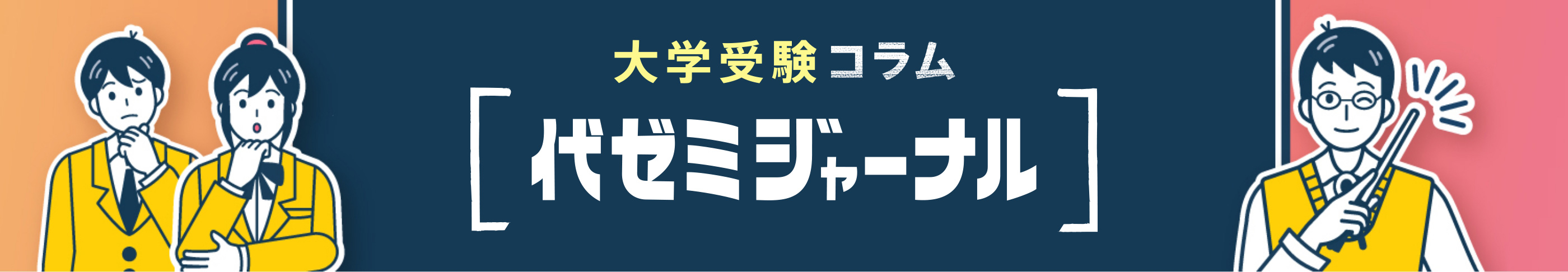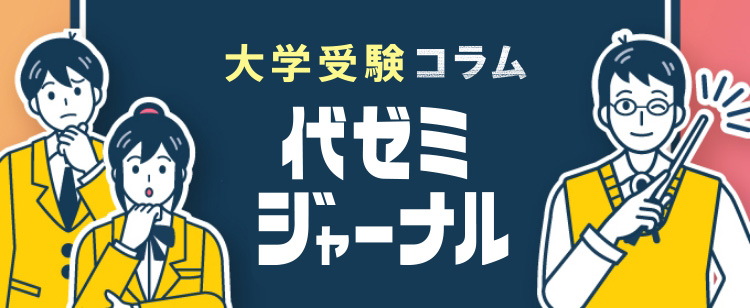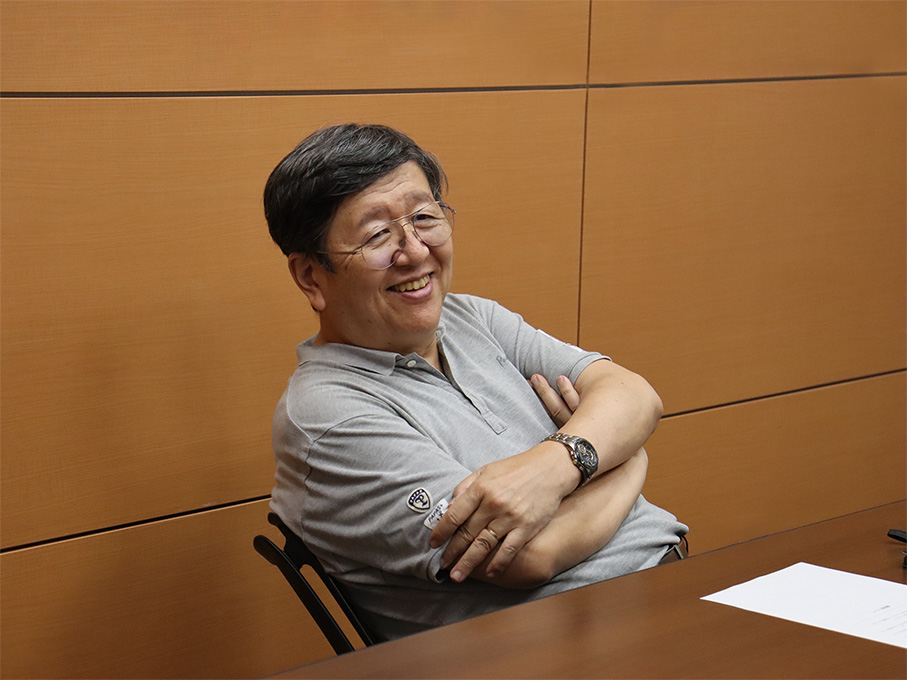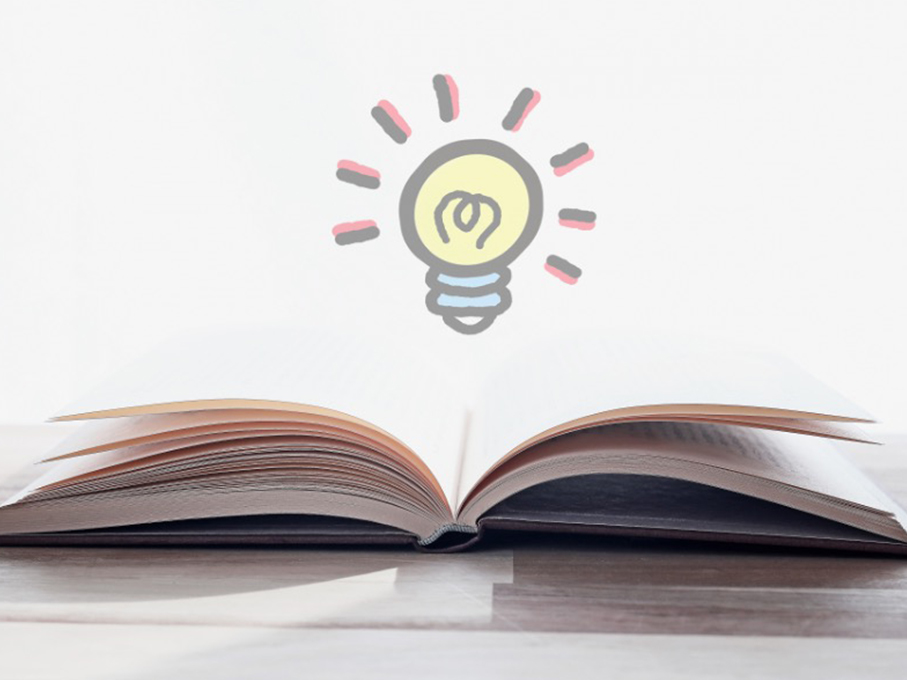2021年度入試からスタートした総合型選抜は、年々実施する大学が増えており、受験者・合格者も増加しています。学力や意欲、適性など、多面的に受験生を評価する総合型選抜で合格するためには、早めの準備がポイントとなります。 今回は、総合型選抜の概要と、学校推薦型選抜や一般選抜(一般入試)との違い、総合型選抜にチャレンジする際に必要なことを解説します。
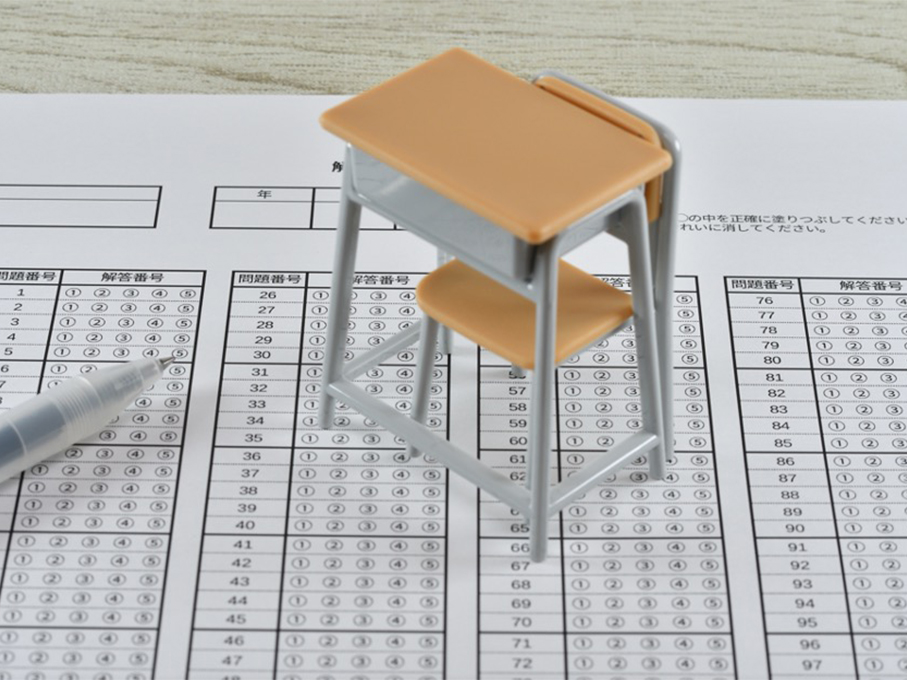
Contents
総合型選抜とは?
総合型選抜は、大学が受験生に求める人物像(アドミッション・ポリシー)と、受験生の学習意欲やポテンシャルとのマッチングを重視する入学者選抜制度です。学科試験の点数だけでなく、エントリーシートや面接、小論文、プレゼンテーションなどを通し、受験生の個性を総合的に評価します。
2021年度入試より、従来のAO入試の名称と内容が変わり、総合型選抜が始まりました。AO入試では人物評価のみで合否が決まることもありましたが、総合型選抜では学力も含めて多面的に評価する大学が多いのが特徴です。
総合型選抜が広まった背景として、昨今のグローバル社会や多様化社会が挙げられます。これからますます複雑化する社会を生き抜くためには、自ら考えて行動する”生きる力”が必要です。社会で活躍する人材を育成するため、大学側も主体性を持って夢や目標を追求する学生を求めており、学力以外の個性や能力も評価する総合型選抜が注目されているのです。
学校推薦型選抜や一般選抜との違い
大学の入試は、大きく分けて「特別選抜(学校推薦型選抜、総合型選抜)」と「一般選抜」があります。総合型選抜の出願は9/1から、学校推薦型選抜は11/1からで、一般選抜は12月下旬からとなっています。
|
|
特徴
|
出願資格
|
選考方法
|
|
|
総合型選抜
|
・大学に入学する意欲が重視される ・専願か併願可能かは大学による |
大学の出願条件を満たすこと |
書類審査、面接、学科試験、プレゼンテーションなど |
|
|
学校推薦型選抜
|
公募制
|
・調査書に記載された高校3年間の成績や取り組みが重視される ・指定校制は主に私立大学の試験方法で、基本的に専願制 |
大学の出願条件を満たし、学校長の推薦があること |
|
|
指定校制 |
大学が指定した高校の生徒で、かつ学校長の推薦があること | |||
|
一般選抜 |
・学力重視 ・何校でも併願可能 |
大学入学資格を満たせば、誰でも受験できる |
・国公立大:共通テスト+個別試験 ・私立大:各大学で試験を実施する一般方式、共通テスト利用方式など |
|
一般選抜が1〜3月に行われるのに対し、総合型選抜と学校推薦型選抜は9〜12月中に実施されるので、「年内入試」と呼ばれます。特に学校推薦型選抜では、高校3年間の取り組みが評価されるので、定期テストや部活などでコツコツ努力を重ねてきた人が有利になります。

総合型選抜を受けるメリット
近年は有名国公立大学でも、総合型選抜を採用する大学が増えています。ここでは、総合型選抜を受けるメリットを3つ紹介します。
学力以外の努力や個性も評価される
総合型選抜では、エントリーシートや、小論文や面接などの試験を通して、自分のことを多面的に評価してもらえます。これまでの実績や意欲次第で、自分の学力以上の大学に合格する可能性もあるので、大学の選択肢の幅が広がります。
受験回数を増やせる
総合型選抜は、原則として専願(合格時の入学を確約)ですが、併願が可能な大学もあります。専願・併願可に関わらず、総合型選抜に不合格になった場合は同じ大学を一般選抜で再出願することも可能なので、志望校を受験するチャンスを増やすことができます。
出願準備の大学調べで、自分自身を見つめなおせる
総合型選抜では、大学の志望理由を深く考え、在学中や卒業後のビジョンを具体的に思い描く必要があり、自分は大学で何をしたいのかを考えるよいきっかけになります。受験のために深く考えた過程は、大学卒業後の進路にも活かせるでしょう。
総合型選抜にチャレンジする際に必要なこと
総合型選抜は、大学・学部によって選考方法が異なるものの、さまざまな書類の提出や試験対策が必要となるため、早めの準備がポイントとなります。以下で、総合型選抜にチャレンジする際に必要なことを解説します。
出願資格を満たす
大学・学部によって、出願資格はさまざまです。中には、語学の資格やコンクール出場経験、課題レポートの提出などが求められることもあります。高1~高3の1学期までに履修した科目の評定から算出した「評定平均値」が基準を満たしていることを条件とする大学や、夏のオープンキャンパス参加が必須の大学もあるので、あらかじめ出願条件をしっかり確認しておきましょう。
志望理由を深堀りし、実績を作る
その大学に行きたい目的が明確にあり、志望理由に基づいた実績があると、強力なPRポイントとなります。たとえば、「将来は国際協力の仕事に就きたいので、高1の夏休みに海外ボランティアに参加した」など、大学側に意欲と熱意が伝わるエピソードを用意しておきましょう。
小論文や面接対策を行う
総合型選抜の選考方法はさまざまですが、小論文や面接による試験が多い傾向にあります。高校の先生や予備校などで小論文の添削や面接対策の指導を受けるなど第三者の力も借りて準備を進めましょう。

総合型選抜は併願もOK! 計画的な受験対策を
総合型選抜は、一般選抜との併願もできます。総合型選抜で不合格となった場合は、すぐに気持ちを切り替えて、一般選抜に臨みましょう。総合型選抜の準備と並行して、一般選抜対策も進めておくと安心です。
総合型選抜の選考方法はさまざまですが、書類の提出や面接対策が必要となるため、できるだけ早く入試の概要と対策のポイントを押さえておきたいもの。代ゼミでは、自己推薦書の書き方や面接対策を学べる、特別選抜対策講座をご用意しています。総合型選抜での小論文の書き方・考え方については、特別選抜小論文講座(基礎編/問題練習編)をご活用ください。
「総合型選抜を検討しているけど、一般選抜の対策もしたい」という受験生も、代ゼミがしっかりサポートします。代ゼミの講師・スタッフと一緒に、あなたにピッタリの受験対策を計画しましょう!