時事王 代々木ゼミナール×読売中高生新聞
2026.1.8
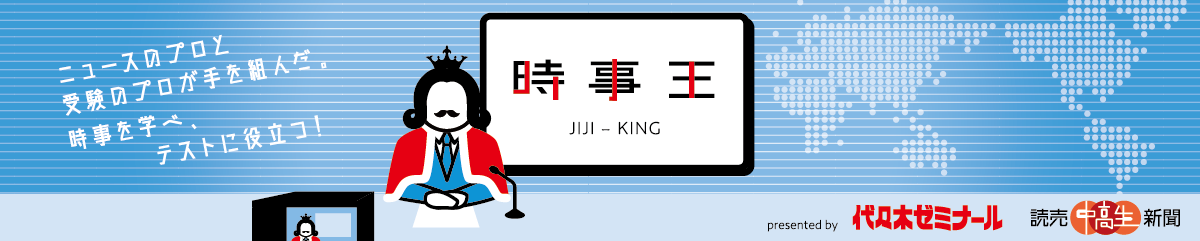
読売中高生新聞「時事王」掲載問題の解答ポイントなどを公開。テストに役立つ時事を学ぼう!
2026年1月9日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
AIを活用していく利点はどのようなことだろうか。資料から読み取り、まとめよう。
【解答例】
・情報を見落とすリスクを減らしたり、自分では思いつけない提案をしたりしてくれること。
・人間の作業を効率化できること。
【解説】
AIを活用している例については、主に資料1で述べられています。医療現場で活用されているAIは、「実際の診断は医師が行うが、見過ごす恐れがあるポイントを再確認できる可能性が高まる」「電子カルテを作るサポートも医師の業務改善につながる」という意見が紹介されているので、人間の作業の効率化やサポートに役立っているということがわかるでしょう。また、資料2では「生成AIを使えば、さまざまな作業が効率化でき、自分には思い浮かばない知恵を授けてくれることもあります」とあるので、こちらもAIを活用する利点と言えそうです。
【問2】
AIを活用していくなかで気を付けなければいけないことはどのようなことか。資料から読み取り、まとめよう。
【解答例】
・必ずしも正しいことを述べているとは限らず、誤った答えを出したとしても、その過程がわからないこと。
・AIを運用するために膨大な機械や電力が必要になること。
・AIを活用する人間の判断や責任を考え直す必要があること。
【解説】
AIを活用することのリスクは、主に資料2で述べられています。生成AIに質問をすれば短時間でなんらかの答えを導き出してくれますが、それが本当に正しい情報であるのかをAI自身が判断することはできません。現時点では答えを導く過程も不明瞭です。つまり、AIの正しさについては人間が判断する必要があり、その責任やリスクについて考える必要があるということになるでしょう。
また、図では経費の面での問題にも触れられているので、ここをまとめるのもよいでしょう。
【問3】
私たちは今後AIとどう付き合っていくべきか。資料から読み取った内容や問1問2で考えたことをもとに、考えてみよう。
【解答例】
AIは私たちの生活を便利にするだけではなく、新しい知見をもたらしてくれるものである。しかし一方で、情報の不明瞭さゆえに人間の判断が不可欠であったり、人の心に寄り添う役割は人間の方が得意であったりという面もあるだろう。私たちはAIに頼り切るのではなく、AIと人間の得意分野を見極め、何を任せるのかを考えながらAIを活用していくべきだと考える。
【解説】
AIのメリットとデメリットについては、問1と問2でまとめました。では、私たちはそれらを踏まえてどのようにAIを活用していけばいいのかということを考えましょう。
AIを活用するのをやめる、もしくは極力使わないようにするという意見を考えた人もいるかもしれませんが、AIが実際に役に立っている現状を考えるとあまり現実的ではありません。
資料1と資料2のどちらにおいても、AIに任せきるのではなく、人間の思考や判断が必要になることが示されていますから、その点を中心にまとめるとよいでしょう。
解答例では、AIに頼り切るのではなく任せられる部分と人間が担うべき部分を見極める必要があるという内容を中心にまとめました。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
答えはブラジリアです。
ブラジルの人口第1位の都市はサンパウロ(約1240万人)、第2位の都市はリオデジャネイロ(約678万人)で、ブラジリアは第3位(約309万人)です。ブラジリアは、大西洋沿岸部に人口が集中しているブラジルで、国土の均衡ある発展のため、人口が少なく未開発の内陸部にリオデジャネイロから移転して首都になった都市です。
【問題1】の問2について
答えは中国です。
2022年の各国・地域の温室効果ガス排出量の割合は、中国が30%で最も多く、アメリカ合衆国の13%が次いで2番目に多かったです。中国は人口が多いことや、「世界の工場」と呼ばれるほど工業が発達するなど、産業に多くの電力を使っていることから温室効果ガスの排出量が多くなっています。
【問題1】の問3について
答えはパリです。
1997
年に、温室効果ガス全般について、先進国による総排出量の削減目標を法的に定めた京都議定書が採択されました。この議定書は、先進国のみを対象としていましたが、その後経済発展著しい新興国による温室効果ガス排出量が急増したため、2015年にすべての国が温室効果ガスの削減目標を設定し、その目標達成のための措置を実施する義務を負うパリ協定が採択されました。
【問題1】の問4について
答えは産業革命です。
産業革命以降、地球の気温上昇が顕著にみられるようになってきました。2024年は、産業革命以降の平均気温の上昇幅が1.55℃を記録しました。地球温暖化の進行抑制のために、世界が協力して温室効果ガスの排出量削減に取り組むことが求められています。
【問題2】の問1について
正解は「ウ」です。
第二次世界大戦後の中国では、国民党との内戦に勝利した共産党が指導する中華人民共和国が建国され、国民党は台湾に逃れて中華民国政府を存続させました。中華民国政府と日本との間には、1952年に講和条約が結ばれて以降外交関係が続いていましたが、1972年に中華人民共和国を「中国で唯一の合法政府」と認める日中共同声明が発表されると、中華民国政府と日本との正式な外交関係は断絶されました。ただし、貿易など民間レベルではその後も密接な関係が続いています。アについて。日本は1894年に勃発した日清戦争に勝利し、翌年に結ばれた下関条約によって清(当時の中国の王朝)から台湾を獲得すると、第二次世界大戦終結までの約50年の間領土としました。イについて。台湾では国民党の一党独裁が長らく続きましたが、1980年代に入ると民主化が進み、初の野党である民主進歩党(民進党)が結成されました。そして、1996年に初めて台湾住民の直接選挙による総統選挙が行われて以降、選挙によって政権交代も起こるようになりました。現在は民進党の頼清徳(ライチンドォー)氏が総統を務めています。
【問題2】の問2について
正解は「集団的自衛権」です。
集団的自衛権は国際連合憲章で認められている、密接な関係の国が武力攻撃を受けた際に共同で反撃できる権利です。日本では日本国憲法第9条で許される自衛権の範囲を超えているとしてその行使を禁じていましたが、2014年に安倍晋三内閣は憲法解釈を変更して限定的な行使の容認を閣議決定しました。そして、2016年に安全保障関連法が施行され、集団的自衛権の限定的な行使が可能となりました。
【問題2】の問3について
正解は「イ」です。
東京電力は福島県の福島第一原発・福島第二原発と新潟県の柏崎刈羽原発の、3カ所の原子力発電所を運用していましたが、2011年の東日本大震災によって起きた福島第一原発事故後、福島第一原発は2012・14年に、福島第二原発は2019年に廃止されました。柏崎刈羽原発も全7基が運転を停止していましたが、2017年に6・7号機が原子力規制委員会の新規制基準に合格しました。そして、2025年11月に新潟県知事が再稼動の容認を表明し、12月に県議会も知事への信任を示す議案を可決したことから、6号機が早ければ2026年1月にも運転を再開する見通しとなりました(2025年12月現在)。東京電力の原発の運転再開は、福島第一原発事故以来初めてとなります。アの茨城県には日本原子力発電の東海第二発電所があります。ウの福井県は関西電力の高浜発電所など、日本で最も原発が集中している県として知られています。エの佐賀県には九州電力の玄海原発があります。
【問題2】の問4について
正解は「ビザ」です。
ビザは査証とも呼ばれる、相手国が入国を許可したことの証明書で、通常は自国にある相手国の大使館などで事前に取得します。ただし、ビジネスや観光など短期滞在の目的で海外へ渡航する際、パスポートがあれば入国できる、つまりビザが免除される国も数多くあります。
