時事王 代々木ゼミナール×読売中高生新聞
2025.7.3
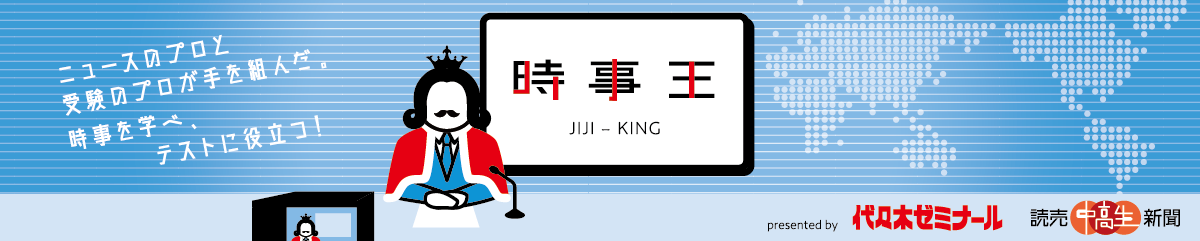
読売中高生新聞「時事王」掲載問題の解答ポイントなどを公開。テストに役立つ時事を学ぼう!
2025年7月4日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
SNSにおける「炎上」とはどのようなことを指すのだろうか。資料1を参考に、SNSの特性も踏まえてまとめてみよう。
【解答例】
SNSは投稿や保存、拡散が誰でも容易に可能であるため、軽はずみな言動などが時として誤解や悪意を伴って広まり、広い範囲で批判を受ける事態となること。
【解説】
「炎上」とは、特定の発信内容や発信者がネット上で多くの批判を受ける現象を指す語です。これには「SNSの特性」も大きく関わっています。資料1に「SNSにアップした情報は誰に保存されているかわからない。削除しても次から次へと再投稿され」とあるように、SNSを介すと誰でも保存や再投稿ができ、簡単に拡散もできて一瞬で多くの人の目に触れてしまいます。したがって近年ではSNSの普及に伴って、より広い範囲で批判や誹謗中傷が巻き起こることがあり、収拾のつかない事態となる場合もあります。また、投稿内容自体が軽はずみで問題があったという場合だけでなく、投稿者に特に非がないと思われるような場合でも誹謗中傷のみが一方的に過熱するといったケースもあり、問題視されています。
【問2】
未成年のSNSやネット利用には、どのようなリスクがあるだろうか。また、リスクを回避するためにはどのようなことに注意するべきだろうか。資料2や図を参考に、考えてみよう。
【解答例】
ネットで知り合った人物と実際に会うことで犯罪に巻き込まれることがある。そのため相手に個人情報を渡すことのないようにし、「闇バイト」の勧誘などへの警戒心を持っておく。また、長時間のネット利用によって学習時間の減少や健康への悪影響などにつながるおそれがある。そのため家庭でルールを決めるなどして利用時間を管理し、長時間の利用にならないように注意する。
【解説】
SNSやネットは便利な反面で様々なリスクもあります。問1の「炎上」もその一つですが、資料2では、オンラインゲームで知り合った人物と接触して詐欺への関与や殺人事件に発展した例が挙げられており、犯罪に巻き込まれる可能性があると言えるでしょう。対策としては、ネットで知り合った人物とむやみに会わないこと、顔写真や連絡先などの個人情報を渡さないことなどが挙げられます。また、図からは、小中高生のネット利用時間が平均してかなり長くなっていることが読み取れ、高校生では1日7時間以上という人が全体の3割以上であることもわかります。長時間ネットに没頭していると、学習時間、さらには睡眠時間の減少を招き、心身の不調などにつながる可能性もあります。対策としては、自分で気を付けられれば最も良いですが、家庭内で使用時間のルールを決めたり,目標時間を設定してスマホを開かないことでクリアとなる脱「依存」ゲームといったスマホ依存対策アプリを導入してみたりするのも一つの手でしょう。
【問3】
近年では未成年のSNSの使用を規制すべきという声も出てきており、2024年3月にはアメリカのフロリダ州で14歳未満のSNSアカウント保有を禁止する法案が成立した。このようなSNSの利用規制の動きについて、あなたは賛成か反対か。その理由を含めて考えてみよう。
【解答例】
(賛成例) 賛成である。未成年、特に小・中学生は適正なSNS利用に必要な判断能力が十分でないと考えられ、犯罪等の危険だけでなく、誤った情報を正しいと信じ込んだり、人間関係のトラブルに発展したりするリスクが大きいため利用を避けるのがよい。連絡手段としての役割なら、電話やメールなどで問題なく代替可能である。
(反対例) 反対である。現在SNSは連絡や情報収集の手段の一つとして欠かせないものとなっているため、たとえ未成年時に規制されたとしても将来的には利用する可能性が高い。ゆえに利用を禁止するのではなく、適正な利用の仕方を身につけることが重要であり、そのためのリテラシー教育などを充実させるべきである。
【解説】
未成年のSNS利用への規制は、問題文にあるフロリダ州の例のほか、2024年11月にオーストラリアでも類似の法案が可決されるなど海外で始まっています。問1・2で取り上げたリスクや弊害を考慮すれば、規制の動きがあることもうなずけるかもしれません。ただ、実際には未成年も高い割合でSNSを使用しており、その利便性・娯楽性を享受しています。それを踏まえた上で、SNSの利用規制への賛否について、自分なりに考えることが重要です。
賛成と考える場合は、上述のようなリスクを重く見た上で、特に未成年の利用を規制すべき理由として、そのようなリスクが危機管理能力や判断力が未熟な未成年には生じやすいことなどが挙げられるでしょう。SNSはワークシートの「(※)」にある通り、LINEなどのメッセージアプリも含みますが、そのような連絡手段としての側面も、電話やメールで代替可能と言うことができます。高機能なスマートフォンではなく、簡易的な機能を持つキッズ携帯やガラホも販売されており、子どもや高齢者に使用されています。
反対と考える場合は、SNSの利便性を重視し、リスクについては規制以外の方法で対策するなどの提案が可能でしょう。SNSは交友関係を広げたり、自分の興味のある情報をリアルタイムで収集できたりと非常に有益な側面があることは周知の通りであり、未成年のうちから利用しながら正しい利用法を習得すべきと考えることができるでしょう。また、SNSのみを禁止しても、その他のネット利用などでリスクが残るといったことに着目することもできます。
問の解答を考えることを通じて、自分自身のSNSやネット利用の仕方についても、今一度見直してみましょう。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
正解はエです。
北海道は47都道府県で最も面積が広く、また有珠山、大雪山、十勝岳など火山が各地にあり温泉地が多いです。登別温泉は北海道の太平洋側にある日本を代表する温泉地です。登別とは先住民アイヌの言葉で、温泉のため色が濃く濁った川という意味の「ヌプルペッ」に漢字をあてた地名です。
アの有馬は兵庫県、イの下呂は岐阜県、ウの道後は愛媛県の温泉地です。
【問題1】の問2について
正解はアです。
温泉法によると、地中から湧出した時の温度が25℃以上あれば温泉となり、25℃未満であっても19種類の成分が規定量以上含まれていれば温泉となります。また条件を満たしていれば水蒸気やガスも温泉となります。温泉が湧き出る源泉は入浴に適さない高温であることが多く、入浴できる施設では41℃前後の水温となるように調整されています。
【問題1】の問3について
正解はアです。
硫黄が含まれる温泉を硫黄泉といいます。火山のマグマに硫黄が溶け込んでいる影響で、硫黄泉の温泉は火山の近くに多く分布しています。硫黄泉は独特のにおいや、白く濁った湯などが特徴的です。なお塩素、窒素、ヨウ素はいずれも温泉法で温泉と認定されるための19種類の成分には含まれていません。
【問題1】の問4について
正解はマグマです。
マグマとは地下にある岩石が溶けたもので、マグマだまりから溶岩や火砕流、火山灰などが地上に出て噴火したところが火山となります。日本列島は4つのプレートの境界付近にあり、太平洋の海洋のプレートが日本列島のある大陸のプレートに沈みこみ、そこで地下深くへと潜った岩石が海からの水で冷やされ溶けやすくなってマグマになると考えられています。海底にあるプレートの境界で深く海底が沈みこんでいる地点を海溝といい、日本列島の火山は海溝に平行して分布しています。
【問題2】の問1について
正解はカシミヤです。
カシミヤの語源はカシミール地方にあります。カシミール地方は、8000メートル級の山々を擁する山岳地帯であり、この山岳地帯にはカシミヤ山羊という山羊が生息しています。この山羊の毛によって作られた毛織物をカシミヤと言い、暖かく軽いことから高級な素材として人気があります。現在では、カシミヤは中国やモンゴルなどで多く生産されています。
【問題2】の問2について
正解は植民地です。
ここでいう植民地は、近世以降ヨーロッパを中心とした列強がアメリカ大陸・アフリカ・アジア各地を、主に軍事力によって獲得して、原料供給地、製品市場として支配した地域を指します。イギリスは、17世紀以来インドに進出して徐々に支配領域を広げ、19世紀後半にはインド・パキスタン・ビルマ(現在のミャンマー)に至る広大な地域を「インド帝国」として支配していました。このインド帝国には多様な民族、宗教、文化を持つ人々が存在していました。
【問題2】の問3について
正解はヒンズー教です。
インドはもともとヒンズー教徒の多い地域でしたが、13世紀以降は、北インドはイスラム王朝の支配を受けていました。そのため、北インドを中心として、イスラム教徒の多い地域が形成されました。その後、イギリスがインド支配にあたって、両教徒の対立を煽るような政策を行ったこともあって、両者の対立は深まりました。イギリスからの独立に際して、イスラム教徒の多い地域はパキスタン、ヒンズー教徒の多い地域はインドとして独立することになりますが、イスラム教徒の住民が多い一方で藩王がヒンズー教徒だったカシミール地方の帰属をめぐる紛争は、現在に至っても解決していません。
【問題2】の問4について
正解はエのバングラデシュです。
1947年、インド帝国においてイスラム教徒の多い地域が、イギリスからパキスタンとして独立しました。この際のパキスタン領は、現在のパキスタンにあたる西パキスタンと現在のバングラデシュにあたる東パキスタンが、同時期にイギリスから独立したインドを挟んで飛び地となっていました。東パキスタンは西パキスタンからは離れており、同じイスラム教徒とはいえ、言語や習俗も西パキスタンとは異なっていました。また、政治的にも経済的にも西パキスタンに従属するような立場を強いられていたこともあって、パキスタンからの独立運動が広がりました。パキスタンはこの運動を弾圧し、独立運動に介入したインドとの間で1971年に第3次印パ戦争となりました。戦争にはパキスタンが敗れ、バングラデシュの独立が達成されました。
2025年6月6日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
「流行」とはどのようなもので、どのようなサイクルを持つか、【資料1】や図1・図2を中心にまとめよう。
【解答例】
消費者が持つ「差別化」「同調化」という2つの欲求を、絶妙なバランスで満たすものの中から生まれるもので、初期にはごく少数だけが利用するが、段階的に利用者が多数派になっていき、ピークを迎えた後は「差別化」の欲求に応えられず、やがて収束する、というサイクルを持つ。
【解説】
【資料1】は2つの段落に分かれており、それぞれが図1と図2に対応するので、内容を簡潔にまとめます。登場するキーワード(今回は「差別化」と「同調化」など)は説明に取り入れましょう。なお、確かに「流行」であるが【資料1】の内容に沿っているとは言えなさそうなもの、つまり【資料1】の反例を考えてみることも、思考の訓練になるでしょう。
【問2】
身近な「流行」を1つ思い浮かべ、その「流行」にあなたがどう関わってきたかを、「差別化」「同調化」の言葉を用いて分析してみよう。また、その「流行」は現在、図2中のどの段階にあるかも考えてみよう。
【解答例】
最近、あるロボットアニメが学校でもSNS上でも「流行」している。私はこれまで、ロボットアニメというジャンル自体に興味がなかったが、クラスの友人がしきりに勧めてくるので、「同調化」して話を合わせたい、という思いが強まり、視聴するようになった。一度視聴すると、どのキャラクターが「推し」であるか、という話題で盛り上がるようにもなったが、自分の「推し」を決める行為は、「差別化」の欲求の表れなのだろう。このアニメは現在、最終回の放映間近だ。おそらく現在がまさに「流行」のピークで、放映が終了し、次の新しいアニメ作品群が放映を開始すれば、「流行」は落ち着いていくのだろう。
【解説】
何であれ、自分の行為や心理を対象化・客観視し、より大局的な視点から冷静に分析する態度を持つことは大切です。「差別化」「同調化」は適用範囲の広い言葉であるので、様々な領域における現象の分析に、広く応用できるでしょう。何かを分析することとは、具体的・特殊な個々の事例を、何らかの抽象的・普遍的な枠組みと関連付けることである、とも言われます。「流行」への熱狂も楽しいものですが、同時にその熱狂について冷静に説明していける自己分析の習慣も持てると、日常の雑談にも深みが出るでしょう。
【問3】
【資料2】では新たな「流行」が生まれる過程を、生産者・供給者側の立場から説明している。これを参考に、問2で思い浮かべた「流行」も、生産者・供給者側の目線から考察してみよう。
【解答例】
振り返ってみるとこのロボットアニメの制作者側は、私たちのような若者向けに、多様なSNSを駆使して、それぞれのSNSの特色を活かした大規模なプロモーション活動を行っていたようだ。SNS上では同世代のインフルエンサーたちもしきりにこのアニメを勧めていたので、もしかすると制作者側から直接宣伝を依頼されていたかもしれない。また、ロボットアニメなのでオモチャなど関連グッズの展開もある。私も何個か購入したので、企業の戦略に典型的に乗せられた行動をとった気もするが、作品自体が面白いので、むしろもっと集めて応援したいという気分も根強い。
【解説】
近年では多くの「流行」はマスメディアからではなく、ソーシャルメディアから生まれる、という指摘もありますが、そうだとしても「流行」の背景では、ほぼ常に巨額のお金が動いている、ということは意識しておいてよいでしょう。そもそもSNSが閲覧されること自体、特定の企業や個人に収益をもたらします。大抵のケースで、中高生は基本的に消費者・需要者側ですが、その裏側にはほぼ必ず、生産者・供給者側の立場や考え方がある、という事実も今から意識しておくと、世の中を見るためのより深い視点が獲得できるようになります。収益を求める者の存在が意識されることで、不自然に「うまい話」に騙されてしまうリスクも減るでしょう。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
答えは「京都府」です。
文化庁は、芸術文化の振興や文化財の保存などの政策を担う、文部科学省の外局です。文化庁が担当する政策の分野は、文化財、美術館・博物館、著作権、日本語、食文化、宗教、観光、国際文化交流など非常に多岐にわたります。
中央省庁が東京都に一極集中している状況の是正や、地方創生を目的として、中央省庁や関連する政府機関などの機能を東京都外へ移す計画は以前から進められていました。その一環として、2023年に、文化庁の本庁および大部分の部署が京都府京都市へ移転されました。なお、著作権など一部の政策を担当する部署については、引き続き東京で業務が行われます。
【問題1】の問2について
答えは「Social Networking Service」です。
SNSは「Social Networking Service」の略で、インターネット上で構築された社会的なネットワーク(Social Network)によって、多くの人と交流や情報発信を行えるWebサービス(Service)のことを指します。「Facebook」や「X(旧:Twitter)」、「Instagram」などが代表例です。
SNSと似た概念に「ソーシャルメディア(Social media)」がありますが、ソーシャルメディアはSNSに加えて、「YouTube」などの動画配信サイト、「LINE」などのチャットツール、「食べログ」などの口コミサイトなどのように、インターネットを通じて互いに情報発信を行うことのできるメディアの総称です。
【問題1】の問3について
答えは「市販のゲームのプログラムをコピーし、別のゲームとして販売する。」です。
著作権は、著作物を作成した人(著作者)の権利や利益を保護することで、著作物を生み出した努力に報いるために設けられています。一方で、他人が生み出した創作を適切に利用し、そこからアイデアや着想を得て新たな著作物を創り出すというサイクルは、芸術や文化の発展において重要な役割を果たしてきました。そのため、著作者の権利の保護を最優先にしてしまうと、このサイクルが機能せず、文化の発展が阻害される可能性もあります。
著作権に関する法律である著作権法は、この「著作者の権利の保護」と「著作物を利用することによる文化の発展」のバランスを調整する役割を担っています。そのため著作権法では、著作物を許可なく使用された場合には、使用の差し止めや、損害賠償の請求ができると規定されていると同時に、著作権の保護対象および保護期間に関する制約規定や、特定の状況では著作者の許可なく著作物を使うことができる例外規定も設けられています。
ア:著作権侵害とはいえない
記事にもある通り、作品そのものには著作権が与えられますが、その作品を創る際に用いた「作風やスタイルなどのアイデア」は著作権の保護の対象となりません。そのため、特定の画家の塗り方を真似てオリジナルのイラストを作成することは著作権違反にはならず、また描いた絵の著作権は描いた本人に与えられます。
イ:著作権侵害といえる
記事にもある通り、著作物にはゲームなどの「プログラム」が含まれます。そのため、著作者の許可を得ずにゲームのプログラムをコピーすることは、著作権に関連する権利(著作財産権)の一つである「複製権」の侵害となります。
ウ:著作権侵害とはいえない
街中で出会った芸能人を許可なく撮影することは、著作権ではなく「肖像権」の侵害となります。肖像権とは、自分の容姿を勝手に撮影され、インターネット上などに公表されないよう求める、プライバシーに関する権利の一つです。著作権と同様に、他人の肖像権を侵害すると損害賠償が発生する場合もあります。
エ:著作権侵害とはいえない
著作者の許可なく小説を翻訳する行為は、著作財産権の一つである「翻案権」の侵害となります。しかし日本では、著作権の保護期間は著作者の死後70年間と規定されており、その期間を過ぎた著作物は著作権の保護の対象から外れます(これを「パブリックドメイン」といいます)。150年前に亡くなった作家の小説は既に著作権が切れているので、翻訳を含め自由に使用することができます。
【問題1】の問4について
答えは「特許」です。
産業財産権は「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の四つの権利の総称です。工業製品やお店に並ぶ商品(量産品)には、原則として著作権が適用されません。その代わり、産業財産権などによって、様々な種類の権利が保護されています。
特許権は、高度な発明によって生み出された技術を保護するための権利です。実用新案権は、特許よりは高度でないものの、物品の形状や組合せにより生み出された技術を保護するための権利です。
意匠権は、物品の形状や模様そのものといったデザインを保護するための権利です。意匠権で保護されるものの代表例として、「自動車の車体」や「ゲーム機のコントローラ」などがあります。近年では「建築物の内装」や「SNS映えするスイーツの盛り付け」などにも意匠権の保護が及ぶようになりました。
商標権は、企業が販売する商品の名称やロゴマークなどを保護するための権利です。例えば、「読売中高生新聞」という名称や、1面上部に掲載されているロゴマークは、読売新聞東京本社が商標権を取得しています。また特許権、実用新案権、意匠権は、それぞれに規定された保護期間が経過すると自動的に権利が消滅しますが、商標権だけは、更新することにより半永久的に保護することが可能です。
工業製品を保護する権利には他にも、半導体回路の設計に関する「回路配置利用権」や、新種の農作物に関する「育成者権」などがあります。これらの権利と産業財産権、そして著作権をまとめて「知的財産権」といいます。
【問題2】の問1について
正解は東京タワーです。
1950年代に入って各テレビ局が独自の電波塔を建てたために電波塔が乱立し、景観が問題視されるようになりました。このため全てのテレビ電波を関東一円に流すテレビ塔の建設が決まり、1958年に完成しました。高さは333mを誇ります。テレビの電波塔としての役割は2012年に完成した東京スカイツリーに移りましたが、現在でもそのバックアップやラジオ波の送信で活躍しています。また、麓の増上寺とともに人気の観光名所となっています。
【問題2】の問2について
正解はイの「世界の記憶」です。
有名な世界遺産とは別の制度です。世界遺産は土地や建造物といった不動産を主な対象としています。一方、「世界の記憶」は新聞記事中にある通り、世界史的に重要と認められた歴史的な文書類を登録対象としています。日本では「増上寺が所蔵する三種の
無形文化遺産もユネスコの制度で、音楽、舞踊、演劇、工芸の技術といったものを対象としたものです。日本からは雅楽、歌舞伎、アイヌの踊り、和食、和紙などが登録されています。重要文化財は日本国内の制度で、有形文化財(絵画、彫刻、建築物など)が対象です。
【問題2】の問3について
正解はアの高麗です。
918年に建国され、936年に朝鮮半島を統一しました。13世紀半ばにモンゴル帝国の侵略を受けて属国となり、1392年に朝鮮王朝によって滅ぼされました。日本史でいう平安時代の中頃から南北朝時代にあたる時期に存在した国です。仏教が盛んに信仰され、木版印刷の技術が発達していたため、多くの仏典を日本に輸出しました。
残りの3つの国は高麗より前の時代の国です。7世紀の朝鮮半島は、北部の高句麗、南東部の新羅、南西部の百済の3つに分かれて争う三国時代でした。このうち最も強大だったのは高句麗でしたが、新羅が中国の唐と結んで百済、高句麗を滅ぼして朝鮮半島を統一しました。日本は百済の友好国であったため、その復興を図って出兵しましたが、663年の白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に敗れています。新羅はその後935年まで続き、高麗に滅ぼされました。
朝鮮半島の統一王朝は、新羅(7世紀後半~10世紀前半)→高麗(10世紀前半~1392)→朝鮮王朝(1392~1910)と移り変わることを覚えておくとよいでしょう。
【問題2】の問4について
正解は法然です。
平安時代末期から鎌倉時代にかけて成立した6つの新宗派は、高校入試でも大学入試でもよく出題されるので覚えておきましょう。法然が開いた浄土宗・親鸞が開いた浄土真宗・一遍が開いた時宗の3つは、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることを重視し、日蓮が開いた日蓮宗は「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを重視しました。一方で、栄西が開いた臨済宗と道元が開いた曹洞宗は禅宗であり、坐禅によって悟りを開くことを勧めました。教科書や資料集に載っている表も使って、各宗派の名前・開祖・教義の内容を整理しておくとよいでしょう。
2025年5月2日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
日本で働く外国人が増えることのプラスの効果について、資料と図から読み取ろう。
【解答例】
・日本における労働力不足の解消に繋がる。
・稼いだお金を日本で使うため、経済効果が生まれる。
・多様な出自や視点を持つ人材が入ってくると、経済が刺激され、活性化する。
【解説】
日本で働く外国人が増えることのプラスの効果については、【資料1】の専門家の話に主に書いてある。解答例の1つ目の、日本における労働力不足の解消に繋がるというのは外国人労働者を受け入れる大きな理由のうちの一つであろう。日本は少子高齢化が進んでおり、労働力人口が減っている。少子高齢化の対策が上手く進んでいない中、外国人労働者の存在は大きい。2025年1月の厚生労働省の発表によると、外国人労働者の数は2024年10月末時点で230万人であり、過去最高を記録した。前年より25万人増加し、対前年増加率は12.4%と前年と同率だった。(読売中高生新聞の記事の図は日本に住む外国人の人数であり、ここに記したのは外国人労働者の人数である)また、外国人を雇用する事業所数は34万所でこちらも過去最多である。このように、外国人労働者の受け入れが広がっていることが分かる。解答例の2つ目の、経済効果については、外国人労働者が日本で生活することによって生まれるものが考えられる。食品や日用品などをはじめ様々なものを日本で購入するため、それにより日本の経済が潤うことが予想される。解答例の3つ目の、経済の活性化については、外国で暮らしてきた人の新たな視点が、新しいアイデアを生むことに繋がり、経済を刺激することが考えられる。日本人だけでは解決できなかった問題も、外国人の斬新な策によって、解決につながるということもあるだろう。
【問2】
日本に外国人を受け入れることの課題について、資料と図を参考に考えよう。
【解答例】
・生活や教育など、外国人を受け入れるための環境整備が不十分。
・移民に関する国民的議論を進めていく必要がある。
・移民に仕事を奪われたり、移民が治安を悪化させたりしているという考えを持つ人がいる。
・多様な文化を持った人々が日本に来ることで文化の摩擦が起きることがある。
【解説】
日本に外国人を受け入れることの課題については、【資料1】【資料2】図のそれぞれを参考に考えることができる。まず、【資料1】の専門家の話の最後に、生活や教育など、外国人を受け入れるための環境整備が不十分ということが書かれている。言語の壁も大きいであろう。いくら街中に英語の表記が増えたとはいえ、日本人向けに作られた生活空間のなかでは、電車一つ乗るのにも一苦労である。また、教育現場でも、日本人の先生がどうやって外国人の子に授業をするか。問題は大きい。さらに、日本での役所の手続きをどうするかといった制度にかかわる複雑な話などもある。次に、【資料1】の後半と【資料2】に日本で移民に関する国民的議論を進めていく必要があることと、移民の多い国には移民への懸念を持っている人がいるということが書かれている。移民への懸念を持つ人は日本にもいると考えられるため、対策が必要だ。まず、国民的議論を進めるためには、移民に仕事を奪われる、移民が治安を悪化させるといった懸念を払拭しなければならない。移民に仕事を奪われるといった点については、ある書籍によると、移民がアメリカ人労働者の雇用水準に及ぼす効果を考察した論文は多数あるが、大半がアメリカ人労働者の雇用を減少させる効果はないと結論付けているとされている。多数の文献を分析した調査でも、アメリカ人労働者の雇用は移民によってほとんど影響を受けていないことを示しているという結果もあり、移民が仕事を奪っているという主張には疑問が残る。また、移民が治安を悪化させるという点については、外国人が犯した犯罪の場合は、報道の見出しに「外国人」が使われるなどし、犯罪をしている外国人が多いという思い込みが助長されるということも関係あるだろう。このような移民への偏見をなくしていく必要がある。また、図を見ると、日本に住む外国人は多様な国々から来ており、日本で文化の摩擦が起きるということも考えられる。ごみ出しの仕方などの生活面の問題もあれば、宗教などの問題もあるだろう。国が違えば「当たり前」の内容も変わってくる。文化の摩擦を一つ一つ解消していかなければならない。
【問3】
日本はどのようにして外国人を受け入れていくべきか。問1と問2で答えたことを踏まえて考えてみよう。
【解答例】
・外国人を受け入れる職場や学校で、宗教などをはじめとした外国人の文化を理解する機会、日本の文化を理解してもらう機会を設ける。
・移住してきた外国人向けの環境整備を、日本に住む同郷の外国人の意見を求めながら行う。
・外国人に対しての偏見を、外国人との交流イベント等を通して一つ一つなくしていく。
【解説】
問1と問2を踏まえて、日本はどのようにして外国人を受け入れていくべきか考える。3月21日の読売中高生新聞の紙面では、取り組みの一例が紹介されていた。ある会社では、外国人労働者の宗教を尊重するために、祈りの場を設けたり、逆に日本の文化を理解してもらうために、茶道や剣道などの体験会を催したりしている。他者と共存するためには、ただ一方的に相手を知ろうとするのではなく、自分のことも知ってもらうことが必要だ。会社においても、一見仕事とは関係のない文化の面も互いに理解し合うことで、仕事をスムーズに行うことに繋がるであろう。これは学校などでも同じ取り組みができる。ほかにも、中国人向けの学習塾を紹介する外国出身の方の例が紹介されていた。やはり、同じ国の出身であれば、顧客のニーズをよく理解しているだろう。日本人が理解するということももちろん大切であるが、外国人に理解の手助けをしてもらうというのも有効である。塾だけではなく、ありとあらゆる生活サービスにおいても、外国人の声を取り入れることが必要になってくる。そして、やはり大切なのは外国人に対しての偏見をなくしていくことである。問2でも触れたが、日本は島国であるためか、外国人に対しての心理的距離が離れていると言われる。日本に来る外国人が増えていくとされる中、相互理解が大切になってくる。外国人と実際に接することを通して、一つ一つ互いへの思い込みをなくしていくことが必要だろう。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
正解はアです。
ASEANは東南アジア諸国連合の略称で、ミャンマー、タイなど10か国が加盟しています。経済の開発、地域の平和・安全を目指す組織で、貿易の拡大なども目的となっています。日本はASEAN諸国と政治的、経済的に強い結びつきがあります。
イのAUはアフリカ諸国が加盟するアフリカ連合、ウのEUはヨーロッパ諸国が加盟するヨーロッパ連合、エのNATOはアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国が加盟する軍事同盟の北大西洋条約機構の略称です。
【問題1】の問2について
正解はエです。
ミャンマーはインドから伝わった仏教が多数派の宗教で、国民の80%以上を占めています。各地に仏教寺院があり、世界文化遺産のバガン遺跡などが知られています。なお近年は、少数派のイスラーム教徒のロヒンギャが弾圧され、難民化するなど問題となっています。
仏教はタイ、ラオス、カンボジア、ベトナムなど東南アジアで広く信仰されています。東南アジアの他の国について、フィリピンはイのキリスト教、インドネシアやマレーシアはイスラーム教が多数派となっています。ウのヒンドゥー教はインドの民族宗教です。
【問題1】の問3について
正解はエです。
タイはミャンマーの隣国で、首都バンコクは政治、経済、文化などの中心で、人口が集中している大都市です。2025年3月28日、ミャンマーを震源とする地震では建設中の高層ビルが崩れるなど、さまざまな被害が出ました。また鉄道やバス、飛行機などの交通機関も一時運行を見合わせました。タイやミャンマーは地震の多い地域ではないですが、今後地震が発生した場合に備えて対策する必要も出てきました。
アのクアラルンプールはマレーシアの首都、イのジャカルタはインドネシアの首都、ウのハノイはベトナムの首都です。
【問題1】の問4について
正解はイです。
政府開発援助ことODAは、先進国が発展途上国に対して行っている援助で、日本はミャンマーに対する最大の援助国です。2021年以降、ミャンマーでは軍による支配が続き、反政府勢力や少数民族との抗争などで政情は不安定です。2024年、日本のODAによりヤンゴン郊外に全長約2.6kmの橋が完成すると、軍を中心とした政府に資金が流れているのではないかと批判が起こりました。
アのNGOは非政府組織で、政府の活動とは別に平和や人権の問題などに積極的に取り組む国際的な民間の団体です。ウのPKOは国際連合による平和維持活動、エのWTOは国際連合の関連機関の世界貿易機関です。
【問題2】の問1について
答えはアメリカ合衆国です。
スターバックスは、1971年にアメリカ合衆国のシアトルで開業したコーヒーチェーンです。コーヒーはアフリカのエチオピア原産ですが、アラビア半島、トルコなどとの貿易を通してヨーロッパに持ち込まれました。エスプレッソコーヒーは、イタリア発祥です。スターバックスは、エスプレッソを主体としたコーヒーチェーンとして開業しました。現在では、コーヒーの他にティーやフラペチーノ等のビバレッジ類を販売しているほか、フードの提供もしています。
スターバックスは、「スターバックスコーヒージャパン」として日本にも進出しています。日本の他、多くの国にも進出しており、世界的に有名なコーヒーチェーンとなっています。
【問題2】の問2について
答えは「海や土の中で水や二酸化炭素に分解されないこと」です。
文章の5~6行目に「新しいストローは海や土の中でも水と二酸化炭素に分解されるため、環境への負荷が低い」とあります。これは、従前のプラスチックストローが海や土の中でも水と二酸化炭素に分解されず環境負荷が大きかったこと、新しいプラスチックストローはこの問題点を克服したことが読み取れます。
【問題2】の問3について
答えは「飲み心地が悪いこと」です。
プラスチック製のストローと紙製のストローの特徴の違いを考えて、答えを推測する問題です。プラスチックは水をはじく一方、紙は水を吸収します。紙製のストローは水を吸収してふやけることや紙特有のざらつく感触などが飲み心地の悪さをもたらします。
2025年4月4日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
「出生数の推移」の図から、1970年代前半の平均的な第1子出産時の母親の年齢は24~25歳程度だと分かる。出生数がほぼ最多だった1948年前後とその約25年後、50年後、75年後の出生数から分かることを挙げてみよう。
【解答例】
第一次ベビーブーム世代(
【解説】
1945年に国内の日本人人口が約7200万人だったところへ、敗戦の時点で海外に残留していた日本人の軍人、軍属(軍の文官・労働者など)、民間人のうち、一部を除く約600万人が1947年末までに引き揚げてきました(「一部」はほとんどの人が中国残留やソ連によるシベリア抑留)。その影響で空前のベビーブームとなり、出生数は1947~49年の毎年、史上最高を更新しました。
わずか3年で当時の日本人人口の1割近くを占め、後に社会を大きく変えたこの世代は、通商産業省(2001年から経済産業省)の官僚であり1970年の大阪万博の企画などで知られた堺屋太一(故人)の1976年の小説『団塊の世代』で注目されました。
団塊の世代が小学1年前後だった時期である1955年の国勢調査では、日本人人口のうち1947~49年生まれ約730.5万人は1944~46年生まれ約510.5万人の1.43倍もあり、大きな公立小学校に例えると、上の学年が平均7クラスなのに対して平均10クラスもあるといった急増ぶりです。なお、1947~49年生まれの外国人はわずか6万人で、同年齢の人口全体の0.8%にとどまっていました。
それから20年後、団塊の世代の女性が第1子を産んだ後の時期にあたる1975年の国勢調査では、日本人の26~28歳の人口約710.2万人に対し、1~4歳の人口は約803.3万人でした。1955年と違い生年別の統計がないので厳密な比較はできませんが、4年かけて団塊の世代を上回る人数になったわけです。団塊の世代の第1子の世代は、後に「団塊ジュニア」とも呼ばれました。また、政府の『厚生労働白書』なども、1947~49年を第一次ベビーブーム、1971~74年を第二次ベビーブームとしています。
ところが、第二次ベビーブーム世代は、大学進学率の上昇で受験競争が厳しかっただけでなく、バブル崩壊の影響で不況とデフレに見舞われ始める1990年代半ばに大学を卒業することになり、パートや派遣社員など非正規雇用のため低所得から抜け出せない若年層が増えた最初の世代となってしまいました。その影響もあって、第二次ベビーブームの日本人の出生数が各年200万人強だったのに対し、団塊ジュニアの女性が第1子(団塊の世代の初孫)を産み始める時期にあたる1998年は120万人台、さらに25年後の2023年は72万人台と、ちょうど0.6倍ずつになり、すなわち4割ずつ減少しているのです。なお、ここでは簡単化のため第1子出産時の母の平均年齢というデータが25歳程度のままと考えましたが、実際には晩婚化により2011年以降30歳を超えて高止まりしています。
【問2】
1970年代などに比べ日本経済は豊かになったはずだが、日本人の婚姻件数・出生数は低迷を続けている。その理由について、【資料3】を参考にして考え、簡潔にまとめてみよう。
【解答例】
他の先進国に比べ婚外子の割合がかなり低い日本社会では、非正規雇用のため経済生活が安定しない人々の増加などで婚姻件数が低迷しているほか、女性の高学歴化などで晩婚化が進み、それらが少子化に直結していると考えられる。
【解説】
OECD(経済協力開発機構)によるやや古いデータですが、婚姻(法律上の結婚)をしていない男女から2006年に生まれた婚外子が全出生数に占める割合を国際比較したところ、日本はわずか2.11%ですが、ドイツ29.96%、アメリカ38.50%、イギリス43.66%、フランス49.51%、スウェーデン55.47%でした(『平成27年版 厚生労働白書』図表1-4-4)。ただしフランスなど、法律婚でなくても簡略な手続で法律婚に準じた法的保護を受けられるという日本にない制度がある点には留意が必要です。
それにしても、日本では結婚しないと子作りに進めないという考えがほぼ常識のようです。そのため、女性の高学歴化などで晩婚化・非婚化が進むと少子化に直結するわけです。ちなみに、第二次ベビーブーム世代がまだ小中学生だった1985年度の四年制大学進学率は男性38.6%、女性13.7%と大差がありましたが、その後は女性の伸びが男性を上回っており、2023年度には男性60.7%、女性54.5%と大差ありません。
ところが、大学進学率が上がってきたにもかかわらず、25~34歳の「役員を除く雇用者」に占める「正規の職員・従業員」の割合(総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」による)は、男性で1988年2月の96.4%から2024年1~3月平均の85.2%へ、同時期に女性は74.1%から69.4%へ、いずれも下がっているのです。非正規雇用のため経済生活が安定しない人が増えるとともに、【資料3】に指摘があるように、結婚や子作りを控えてしまい、少子化が進んできたと考えられます。
【問3】
日本人の少子化を止めることは困難だとして、外国から現役世代やその子供たちを正式に移民として迎え、社会の支え手の減少に歯止めをかけるべきだという意見がある。それに対するあなた自身の賛否とその理由について考え、簡潔にまとめてみよう。
【賛成例】
社会保障を維持できないレベルの現役世代の減少や人手不足が予想されるので、移民を迎えるのには賛成だ。ただ、外国人との文化摩擦で日本社会が壊れてはいけない。例えば親世代にも日本語教育をきちんと受けてもらい、文化摩擦を軽減することが必須条件だろう。
【反対例】
トランプ政権のほか欧州でも反移民の動きが活発であるのを見ると、多数の移民との共生は困難だと考える。移民をできるだけ抑制し、一方で日本人の正規雇用を増やして若い世代の経済生活の安定を実現し、日本人人口の減少に歯止めをかける方向を追求したい。
【解説】
先進国共通で移民反対の動きが活発化しています。移民を家族ごと受け入れる制度が例外的である日本では、外国人が在留期限を越えて日本に在留しているとか、そもそも在留資格がないのに日本へ入国したといった、不法滞在・不法残留が注目されてしまい、まっとうな移民との共生はあまり話題になりません。不法滞在・不法残留の問題は無視できませんが、例えば国際結婚が破綻して在留資格を失うといった個別の事情もあるので、よく知らない不法滞在・不法残留の問題にこだわるのは不適当でしょう。
それでも、例えばイスラーム教徒が土葬の用地を確保することを地元民が認めないなどといった摩擦は多数の事例がネット上で見られます。それを避けるため移民をできるだけ抑制するなら、【資料3】などから「反対例」のような対策が考えられるでしょう。
ところが、【資料1】から分かる少子化の加速のため、社会保障を維持できないレベルの現役世代の減少や人手不足が不可避だとも考えられます。外国人との摩擦をできるだけ抑制するなら、不十分と言われている日本語教育を最優先にするという「賛成例」のような考え方が有効かもしれません。
いずれにしても、この問題は現在進行形のため、まだまだ考え続ける必要があります。予断をもたず、できるだけ広い視野で考えていきましょう。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1(1)について
正解はアです。
メキシコ湾に接するアメリカの州は5つあり、西からテキサス州(地図上のa州)、ルイジアナ州(地図上のb州)、ミシシッピ州、アラバマ州、フロリダ州となります。カリフォルニア州は太平洋に接するアメリカ西海岸の州で、アメリカの州の中で最大の人口を誇ります。
【問題1】の問1(2)について
正解は油田です。
テキサス州やルイジアナ州のメキシコ湾岸部では、20世紀に入ってから海底油田の開発が進められ、多くの石油工業都市が発達しました。このメキシコ湾岸油田は、アメリカ国内でも2番目の規模を誇ります。なお、アメリカ国内で最大の油田は、アラスカ州北部のプルドーベイ油田です。
【問題1】の問2について
正解はウです。
【問題1】の問3について
正解は歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の中から1つ。
北方領土とは北海道の東に位置する、
【問題2】の問1について
正解は日本放送協会です。
1924年11月に発足した(社団法人)東京放送局は、1925年3月、東京芝浦仮放送所で初のラジオの電波を出し、同年の7月に愛宕山の新局舎で本放送を開始しました。その後、ほぼ同時期に発足していた大阪・名古屋の各放送局を統合し、翌1926年に日本放送協会(NHK)が設立されました。戦後、1950年に特殊法人として改めて発足した日本放送協会は、1953年には日本初のテレビ放送を開始し、1989年には衛星放送も開始しました。その特徴として民間の放送局とは異なり、広告放送などの営利事業は認められず、テレビ放送の受信機を設置した世帯が払う受信料がその財源となっていることが挙げられます。ただ、多様なメディアが展開されている昨今では、テレビ放送の受信機を設置しただけで受信料を払わなければならないNHKの公共放送の仕組みに対して疑問を持つ声も現れてきています。
【問題2】の問2について
正解はプロパガンダです。
プロパガンダ(Propaganda)とは、特定の意見や信念を広めるために情報を操作し、感情に訴える手法、活動を指します。単に「宣伝」と訳されることもあります。現在では政治的、社会的な目的で使用されることが多く、拡散される情報には真実性や客観性が欠如していることもあります。戦前にプロパガンダを巧みに利用した歴史上の例として挙げられるのが、ドイツのナチ党です。1933年にナチ党が権力を握った後、アドルフ・ヒトラーはヨーゼフ・ゲッベルスが指揮する国民啓蒙・宣伝省を創設しました。この省の目的は、美術、音楽、演劇、映画、書籍、教材、新聞やラジオを通じてナチ党のメッセージを確実に広めることでした。こうしたプロパガンダの運動によって、反ユダヤ主義や総統崇拝などを浸透させ、ナチ党の目的に沿って国民の考えを誘導したと言われています。
【問題2】の問3について
正解はアです。
全て1945年の出来事ですが、それぞれの出来事がどのような順番で起こったのか太平洋戦争の流れとともに把握しておくことが受験などでも重要です。1941年12月8日に日本陸軍がイギリス領マレー半島に奇襲上陸し、日本海軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃したことで、太平洋戦争が開始されました。戦争で日本が劣勢に立たされる中、1945年4月、アメリカ軍は沖縄本島に上陸したことで沖縄戦が本格化し、6月23日に組織的な戦闘が終結しました。その戦いの中で沖縄の多くの市民が戦争に動員され、そして多くの犠牲者を出すこととなりました。同年の8月にアメリカは日本を降伏させるべく6日に広島に、9日に長崎に原子爆弾を投下し、広島では約14万人以上、長崎では約7万人以上が犠牲となりました。さらに、広島と長崎への原爆投下の間の8月8日に、ソ連がヤルタ協定に基づき、日ソ中立条約を破って対日参戦し、満洲や朝鮮に侵攻しました。その後、政府は14日にポツダム宣言を受諾し、その翌日の15日の正午、昭和天皇のラジオ放送で全国民に戦争の終結が発表されました。
2025年3月7日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
デジタル教科書を用いることで懸念されている学習上のデメリットを、資料と図を参考にしながらいくつか挙げてみよう。
【解答例】
・デジタル教科書のための端末を用いて、生徒が授業と無関係な内容に集中してしまうおそれがあること。
・画面上で見た情報は記憶に残りにくいという研究結果があり、学力低下のおそれがあること。
・通信環境や表示端末のトラブルによって、授業を中断しなければならないおそれがあること。
【解説】
資料1では、生徒が端末を操作し、授業と無関係な内容に集中してしまうという教員の意見が述べられています。資料2では、一度進めたデジタル化を見直したというスウェーデンの状況が説明され、デジタル化によって生徒の成績が落ちたり、集中力が続かなかったりといった学習上のデメリットが生じたこと、また画面上の情報は記憶に残りにくいという研究者の意見が挙げられています。
「通信環境次第でエラーが起きる」「端末のフリーズ」「視力の悪化」など技術的な問題点もデジタル教科書のデメリットとして資料と図から読み取ることができます。
【問2】
資料と図では言及されていないデジタル教科書のメリットを、自分で考えていくつか挙げてみよう。
【解答例】
・障がいを持つ生徒などこれまでの教科書では不便を感じていた人も、文字の拡大や読み上げの機能などを用いて学習がしやすくなる。
・デジタル教科書のデータを用いて黒板上の掲示や配布プリントを作成することで、教員の授業準備の負担が減る。
・社会時事や科学的発見など、新しい情報を学習に反映しやすくなる。
【解説】
「自分で考えて」とありますが、資料や図を手がかりにしてはいけないということではありません。デジタル教科書は文字の拡大や読み上げ、音声や動画の再生が容易であること、また紙の教科書は「何冊も持ち運ぶのは重たい」が、デジタル教科書ではそれが解消されることといった、資料や図から読み取れることを発展させて、解答を考えましょう。
文字の拡大や読み上げの機能は、英語の発音や漢字の細かい部分の確認などの他、視覚や聴覚に不自由を感じている生徒、また文章を読んだり書いたりすることに困難を感じている生徒が学習しやすくなると期待できます。
また文字の拡大ができるということに、資料では言及されていない教員の授業準備という視点を加えると、紙の教科書に比べて文字や図の加工がしやすく、黒板上の掲示や配布プリントなどを作成する負担が減ると考えられます。音声や動画の再生が生徒それぞれのデジタル教科書上でできることも、再生機器の準備といった負担の軽減につながるでしょう。
さらに、デジタル教科書では社会時事や科学的発見など、紙の教科書では難しかった新しい情報の更新が容易になると期待できます。現在考えられている制度ではデジタル教科書も紙の教科書と同じ内容を表示するということになっていますが、デジタル教科書の表示に使用している端末を用いて、インターネット上の新聞記事や論文などを参照することは、紙の教科書のみを用いている場合よりも容易になるでしょう。
その他、芸術、家庭科、体育など鑑賞や実技指導が必要な教科においてデジタル教科書を用いれば、画像の拡大、音声・動画を個人の端末で再生できることで効果的な学習が期待できる、などの解答も考えられるでしょう。
【問3】
デジタル教科書のメリットを生かし、デメリットを解消するにはどのような工夫が必要か。デジタル教科書の具体的な使用場面を想定した上で、考えてみよう。
【解答例1】
英語の授業において、リスニング・スピーキングではデジタル教科書を、ライティング・リーディングでは紙の教科書を使用する。英語の音声や発音方法の動画を確認することでデジタル教科書のメリットを生かし、単語や文法事項といった、しっかりと覚えたい情報は紙で確認することで、画面上の情報は記憶に残りにくいというデジタル教科書のデメリットを補うことができる。
【解答例2】
学校の授業では基本的に紙の教科書を用い、自宅での予習・復習にはあらかじめ端末にダウンロードしておいたデジタル教科書を用いる。何冊もの教科書を通学で持ち運ぶ必要がないことでデジタル教科書のメリットを生かし、授業では紙の教科書を用いることで、授業中に授業内容と無関係なことに集中してしまう可能性があるというデジタル教科書のデメリットを解消することができる。またあらかじめダウンロードしておくことで、通信環境に左右されずにデジタル教科書を用いることができる。
【解説】
デジタル教科書の効果的な使用方法を、具体的な使用場面を想定して考える問題です。「紙とデジタルの教科書の英語授業での活用状況」のグラフを見ると、「併用している」という解答が合計9割近くを占めています。ここから、紙とデジタル、両教科書の併用ということが、デジタル教科書を効果的に使用する手立てであると考えられます。
では、どのように使い分けたらよいのでしょうか。解答例1は、学習する領域の特性ごとに、紙の教科書とデジタル教科書を使い分けるという提案です。画面上の情報は記憶に残りにくいというデメリットは問1でも取り上げました。これは、しっかりと記憶する必要がある単語や文法などの領域では紙の教科書を用いる、という使い分けで解消できます。音声や動画の再生が容易だというメリットは、資料1にもある通り英語のリスニングやスピーキングの学習に役立ちます。
解答例2は、学習する場所によって使い分けるという提案です。授業中に授業と無関係なことに集中してしまうこと、また通信環境への懸念というデメリットは問1でも取り上げましたが、授業中は紙の教科書を使い、自宅で用いるデジタル教科書についてもあらかじめ教科書内容をダウンロードしておくことで解消できます。複数の教科書を持ち運ぶ負担がなくなるというメリットも、紙の教科書は授業用として学校に置いておき、家では同じ内容のデジタル教科書を用いて予習・復習を行うことで生かせます。
この他、芸術での鑑賞、体育での競技ルールやプレイフォームの確認、家庭科での手順の確認など実技教科にはデジタル教科書を用いるが、記述が求められる教科では紙の教科書を使用するなどの使い分けも考えられます。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
正解はアです。
1995年1月17日午前5時46分、兵庫県の
淡路島は本州と四国の間にある島で、現在は
【問題1】の問2について
正解はイです。
気象庁は国土交通省の外局で、天候などの気象現象だけでなく、自然災害から国民の財産・生命を守るための防災気象情報などを発信しています。地震は津波や土砂災害などの二次災害をもたらすため、気象庁による震度や津波注意報や警報、被害状況の発表は国民の生活や安全のために非常に重要となってきます。
環境庁は公害対策などのために1971年に設置され、2001年から現在の環境省となりました。消防庁は総務省の外局で、自然災害が発生した際には消防や救急などの仕事をします。文化庁は文部科学省の外局で、2023年に東京から京都へ移転しました。
【問題1】の問3について
正解はウです。
2024年1月1日午後4時10分、石川県の能登半島でマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生し、
【問題1】の問4について
正解は直下(断層)です。
「直下型地震」とは、震源の直下にある活断層が動くことによって発生する地震で、断層型地震と呼ばれることもあります。直下型地震は震源が浅く縦揺れが突然襲うため、被害が大きくなりやすいとされています。一方、4つのプレートが集まる日本では、海洋のプレートが大陸のプレートの下に沈む
【問題2】の問1について
正解はイです。
発酵食品とは、微生物が発する
【問題2】の問2について
正解はアです。
酵素とは、化学反応を促進する
【問題2】の問3について
正解はユネスコ無形文化遺産です。
無形文化遺産とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や生活風習などと密接に関わっているもののことをいいます。2003年にユネスコ(国連教育科学文化機関)総会で採択された無形文化遺産条約では、無形文化遺産を保護するために国際的に協力することが定められました。米やこうじなどを用いた日本の伝統的酒造りは、技術が各地の
【問題2】の問4について
正解はアです。
農林水産省の令和5年度食料需給表によると、2022年度における重量ベースの日本の大豆の自給率は6%です。ただし、日本の大豆需要のうち約7割が
2025年2月7日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
日本の一般的な世帯構成は、戦前から近い将来にかけてどのように変化しているか、資料1を参考にまとめよう。
【解答例】
○戦前は、両親とその子ども夫婦、孫の「3世代同居」が一般的だった。
○戦後の高度経済成長期に、両親と同居しない人が急増し、「核家族」世帯が増えた。
○2000年代以降は、世帯の単身化が進んでいる。
【解説】
簡単に言えば、「3世代同居」→「核家族」→「単身」という変化だとまとめられます。「単身」の理由はさまざまで、高齢夫婦の一方が亡くなったことで単身になる場合に加え、そもそも結婚しない人々が多くなったことも背景にあります。
なお、未婚者が結婚しない(独身でいる)理由には、「結婚するにはまだ早い(若い)」、「結婚する必要性を感じない」、「今は仕事(学業)に打ち込みたい」、「適当な(理想的な)相手がいない」、「(独身の)自由さ・気楽さを失いたくない」など、積極的な結婚の動機がないことが挙げられています。
【問2】
65歳以上の単身世帯が増加することに伴って、どのようなことが問題点となるだろうか、資料2を参考にして挙げてみよう。
【解答例】
○政府(国・地方自治体)の財政が逼迫し、現役世代の負担が増えること。
○医療・介護を中心に全般的な分野での担い手(働き手)不足が深刻化すること。
【解説】
上記の【解答例】は65歳以上の単身世帯の増加による影響や課題と言えます。サポート体制を拡充したり担い手の不足を解消したりするには、政府による支援も必要となりますが、政府には社会保障費の支出の増大や税収の減少など、財政的な問題・課題があります。また、全般的な分野での担い手不足により、外国人労働者が増加しています。厚生労働省によると、企業が外国人を受け入れている理由の過半数は人手不足であり、政府も2019年に「特定技能」という在留資格を新設するなど、外国人労働者を受け入れる制度を整えています。これらの他にも、独り暮らしをする高齢者自身の問題もあるでしょう。例えば、足腰が弱って移動が不自由である、入院によって自宅のペットの世話ができなくなる、亡くなった時の遺品処理に公共の費用がかかる、などが挙げられます。
【問3】
問2で挙げた問題点の解決・改善のためにできること(すべきこと)は何だろうか、考えてみよう。
【解説】
問2の【解答例】で挙げられた問題点を解決・改善するには、単身世帯の高齢者をつくらないための方策が必要です。その方策を考える上では、行政ができること(公助)だけでなく、私たちが一個人としてできること(共助)、高齢者自身ができること(自助)などのように、考え方の側面は複数あります。それぞれができることを挙げると、以下のようになります。
公助
=行政ができること(すべきこと)=
○独り暮らしの高齢者を(在宅医療や介護、日常的な見回りなどで)サポートする体制の拡充・強化を図る。
○医療や介護に従事する人々への、制度上の支援を行うことで、負担が重くなり過ぎないようにする。
○結婚や子育てをしやすくしたり、離婚や死別などをしても再婚しやすい風潮を作ったりする。
○上記を行うための財源の確保を、増税・減税などさまざまな方法やそれらの影響を含めた議論を活発にした上で、住民の負担がなるべく少なくて済むようにする。
共助
=私たちが一個人としてできること(すべきこと)=
○関連するボランティア活動があればそれに参加し、担い手不足を解消・解決するために自身でできることはないか、常に考える習慣をつける。
○自身が住む地域の共同体(コミュニティ)の一員であることを自覚して、地域の(特に独り暮らしの)高齢者と関わる機会を大事にする。
○結婚する(結婚に向けて行動する)。
自助
=高齢者自身ができること(すべきこと)=
○心身が元気なうちに、来るべき時に備えておく(高齢者自身の住環境の整理、病院や介護施設への入所の備え、亡くなった時の相続など)。
総務省統計局のデータによると、少子高齢化などにより、日本の総人口は2011年以降12年連続で減少しています。また、合計特殊出生率が過去最低を更新したなどのニュースを耳にしたこともあるでしょう。単に人口が減ったという話ではなく、人口の減少によって生じる問題・課題や、それらを解決・改善するには何をすべきなのかを考え、行動に移す必要があります。決して他人事ではない問題であるため、私たち一人ひとりが自分自身の問題であることを自覚し、できることから一つずつ積み重ねていくことが求められています。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
正解は「首里城」です。首里城は沖縄県那覇市に所在し、明治時代初めに沖縄県が設置される以前は琉球王国の王城でした。第二次世界大戦前にあった正殿などは1945年の沖縄戦によってほとんど焼失してしまいましたが、戦後の沖縄の本土復帰後に復元が本格化し、1992年に完成しました。復元された首里城は、2000年には城壁などの遺構が「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の首里城跡として世界文化遺産にも登録されていましたが、2019年10月の火災で正殿などが全焼し、現在も復興作業が続いています。この年は4月にフランスのノートルダム大聖堂の火災もあり、国内では京都で文化財関係者による防火対策会議が行われるなど、文化財施設における防火体制の見直しが進められました。
【問題1】の問2について
正解は「ナポレオン(ナポレオン=ボナパルト、ナポレオン1世)」です。ナポレオンは、1804年に国民投票で皇帝となり、パリのノートルダム大聖堂で戴冠式を行いました。1789年に始まったフランス革命によって、国王が処刑されて共和政が始まりましたが、政治は安定せず1799年にエジプト遠征から帰国した軍人ナポレオンがクーデタを起こして独裁政権を打ち立てました。ナポレオンは国内の政治改革を進め、皇帝となってヨーロッパ各地を征服して権勢を誇りましたが、解放戦争に敗れ、最後は大西洋のセントヘレナ島に流刑となって死去しました。
【問題1】の問3について
正解は「エ」です。ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所は、第二次世界大戦中にナチス・ドイツが行ったホロコースト(ユダヤ人などへの迫害)の象徴とされる収容施設です。二度とこのようなことが起こらないようにという願いを込めていわゆる「負の世界遺産」として世界文化遺産に登録されています。アの「ケルン大聖堂」はドイツ、イの「タージ・マハル」はインド、ウの「万里の長城」は中国に所在する世界遺産です。
【問題1】の問4について
正解は「ア」です。2019年以降の出来事に当てはまらないものを選べばよく、「トランプが初めてアメリカ大統領に就任した」のは2017年1月のことです。その後、2020年の選挙で民主党のバイデンに敗れて退任することになりましたが、2024年11月の選挙で再選を果たしました。イの「ロシアがウクライナに侵攻した」のは2022年2月で、現在も戦闘が継続しています。ウの「新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に問題化した」のは主として2020年1月以降のことです(中国武漢市で2019年12月に報告)。東京オリンピックの開催延期などをはじめ、社会的・経済的に大きな影響があったことは記憶に新しいでしょう。
【問題2】の問1について
正解(適当でないもの)は、「ア」です。「それぞれの会社で株式を保持することができる」というのは不適当で、経営統合の場合は、新設する親会社(持株会社)が子会社の株式を保有(完全子会社化)する形で統合がなされます。親会社は子会社の管理に徹し、株主の権利を行使して経営に介入することができます。「経営統合」は複数の会社を一本化する「合併」と比べて緩やかな結合となり、元の会社は独立して存続するため、イの「人事制度などを統一する必要がない」、ウの「ブランドや企業文化を維持することができる」といったことがメリットに挙げられます。一方で、グループ内で部門が重複して無駄なコストが生じやすいことなどがデメリットとして指摘されます。
【問題2】の問2について
正解は「トヨタ」です。トヨタ自動車は、愛知県豊田市に本社を置く日本最大手の自動車メーカーです。自動車販売台数は1123万台(2023年)と世界1位を誇り、世界的に日本を代表する企業の一つとみなされています。その源流は、小型力織機の考案などで知られる豊田佐吉が1926年に設立した株式会社豊田自動織機製作所にあり、その自動車部門が1937年にトヨタ自動車工業として独立しました。現在は、ダイハツ工業や日野自動車などを子会社として傘下に入れています。
【問題2】の問3について
正解は、「エ」のドイツです。フォルクスワーゲングループは、ドイツのヴォルフスブルクに本社を置く世界有数の自動車メーカーです。1938年に小型自動車「タイプ1(ビートル)」の生産を始め、第二次世界大戦後には生産モデルを増やしつつヨーロッパの主要な自動車メーカーを次々と傘下に入れてブランド力を大きく拡大しています。日本にも1953年以降に同社製の自動車が輸入されており、現在日本における事業拠点は愛知県豊橋市に置かれています。
【問題2】の問4について
正解は「SDGs」です。SDGs(エスディージーズ)とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、「貧困の根絶」「ジェンダー平等の実現」「気候変動への対策」といった17の目標の下に169の達成基準などが定められた国際目標です。2015年9月の国連総会において、2030年までの達成を目指して採択されました。イメージされやすい環境的な問題だけでなく、差別や貧困といった社会的・経済的な問題についても、「誰一人取り残さない」持続可能なよりよい社会の実現をめざすための目標として設定されました。日本では、政府が2017年以降SDGs達成に向けた優れた取り組みを行う企業・団体を表彰するなど、目標達成への推進をはかっています。
2025年1月10日号
A面「ワークシート」の解答ポイント
【問1】
子どもや若者がSNSを利用することの問題点を、資料や図も参考にしながら、いくつか挙げてみよう。
【解答例】
・性犯罪などの被害にあう危険性があること。
・ネットいじめに加担したり、被害にあったりする可能性があること。
・暴力的な映像などが目に入り、影響を受けてしまう可能性があること。
・闇バイトの勧誘にあう危険性があること。
・スマホ依存に陥り、他の活動に支障が出る可能性があること。
・個人情報などをうかつに公開してしまう可能性があること。
【解説】
資料では、SNSの規制が求められている背景として、「SNSを通じた性犯罪やいじめの横行や、暴力的な映像の拡散」が指摘されているので、これらが答えとなりそうです。また、図にはそのほかに「闇バイト」「スマホ依存」の文字もあるので、これらも挙げるとよいでしょう。特に「スマホ依存」については、グラフでも高校生の1日あたりのSNS利用時間が非常に長いことが示されています。資料にも、オーストラリアのアルバニージー首相の言葉として「子どもたちには端末から離れ、フットボール場などに出かけてほしい」とあり、ここからもスマホ依存に対する懸念を読みとることができるでしょう。
資料や図にはない問題点を自分で考えても構いません。解答例では個人情報をうかつに公開してしまう例を挙げました。ほかに、手に入らないほど高価な品物に憧れて心を病んでしまう、極端な思想ばかりを目にして自分の思想も極端なものにしてしまう、なども挙げられそうです。
【問2】
問1で挙げたような問題を克服するにはどうしたらよいだろうか。子どもや若者のSNS利用を全面的に禁止すること以外の方法を考えてみよう。
【解答例】
・闇バイトでありがちな外部サイトへの誘導を断れるようにするため、保護者が不適切なサイトや動画、アプリをあらかじめ設定し、子どもが利用できないようにする。
・ネットいじめをいちはやく発見するため、保護者が子どものアカウントを確認できるようにする。
・子どもが暴力的な動画を見てしまわないようにするため、子ども専用の新しいプラットフォームを作成する。投稿するまえに内容を検閲するなど、強い規制をかける。
・スマホ依存に陥らないようにするため、子どものSNSの利用に時間制限をかける。
・個人情報を公開できないようにするため、子どものアカウントは投稿ができないようにする。
【解説】
資料2では、文教大学の池辺教授が「利用を制限しても、いずれは触れなければならない。一定の年齢に達した後は自己責任とする考え方もあるだろうが、それでは子どもたちも不安に感じるだろう」と述べています。つまり、現代社会ではSNSが必須である以上、子どもや若者のSNS利用を禁止しても、結局大人になってからSNSのさまざまな問題に直面してしまうということです。だとすれば、大人になって突然触れるよりも、子どもや若者のうちから扱い方を学んだほうがよいともいえるでしょう。
では、子どもや若者が危険を避けながらSNSを使うにはどうしたらよいのでしょうか。同じく池辺教授は「不適切なサイトや動画の閲覧、アプリのダウンロードを制限する機能を使い、大人に保護された状況で、SNSの利用に段階的に慣れていくのが望ましい」としているので、これを使った答えが書けるでしょう。また、自分で他の方法を考えてみても構いません。その際、問1も参考にしながら、どのような問題に対する対策なのかも明確にしておくとよいでしょう。
【問3】
日本でも子どもや若者のSNS利用を制限する法律を作るべきだろうか。作るとすれば、どのような制限とするべきだろうか。あなたの考えを、理由も合わせて書いてみよう。
【解答例1】
日本では、子どもや若者専用の、強い規制のかかった新しいSNSを作って、それ以外のSNSの利用を禁止する法律を作るべきだ。誰でも自由に投稿できるSNSでは、子どもや若者に有害な投稿を全て削除することは難しい。規制の強いSNSを新たに作り、子どもや若者がSNSに慣れるための環境を整えるべきだ。
【解答例2】
日本では、子どもや若者のアカウントを保護者が確認できる機能を作り、また、子どもがアカウントを作るときには保護者の同意が必要となる法律を作るべきだ。SNSの問題は、保護者の目が入ることで対処できるものが多い。利用を全面的に禁止するのではなく保護者が管理するための法律を作り、それ以上は各家庭でルールを作ればよい。
【解説】
子どもや若者のSNSの利用を制限する法律を作るべきかどうか、あなたの意見を述べる問題です。
子どもや若者がSNSを利用すると、問1のように深刻なリスクにさらされることになります。全面的に禁止してしまえば子どもや若者を守ることができますが、資料2から分かる通り、SNSを使わないまま大人になり、うまく付き合う術を身につけていなければ、大人になってから結局は同じ問題に突き当たることになります。
解答例1と2はどちらも全面禁止以外の制限をかけ、子どもや若者の安全の確保と情報社会を生き抜くための学びをうまく両立する方法を模索してみました。解答例1は子どもと若者専用の新たなプラットフォームを作り、そこでの投稿を強く規制する案です。解答例2は、SNSの利用の仕方はあくまでも保護者が監視、指導するものとして、法律では保護者の介入を根拠づけるにとどめました。悪質な投稿に子どもの目が触れる確率を減らせるのは1の方でしょうが、2は子ども一人ひとりの特性や年齢に合わせてより柔軟に対応することができるでしょう。規制と自由のどちらをどの程度重視するかは考え方次第です。
もちろん、子どもや若者のSNSの利用を全面的に禁止すべきだ、もしくは全く制限をかけるべきではないという主張をしても構いません。その際は、将来SNSを利用するときの不安をどう緩和するかや、SNS上に存在する問題にどう対処するかも合わせて書けるとよいでしょう。
B面の解答ポイント
【問題1】の問1について
正解は「間接(選挙)」です。大統領や首相など国家の首脳を選ぶ選挙には、アメリカ合衆国や日本国を含め、大多数の国で間接選挙が採用されています。アメリカの大統領選挙では、有権者は州(およびワシントンD.C.)ごとに「選挙人」団を選出し、この選挙人たちの投票によって大統領が選出されます。そして選挙人団の選挙においては、最多の票を獲得した政党がその州に割り当てられた数の選挙人のすべてを獲得する「勝者総取り」(Winner-take-all)方式と呼ばれる特異な仕組みがとられています(ネブラスカ州・メーン州のみは、小選挙区との並立制)。この仕組みにより、2016年に行われたアメリカ大統領選挙では、選挙人の選挙で民主党(ヒラリー・クリントン候補)に投票した有権者の総得票数が共和党(ドナルド・トランプ候補)を上回っていたにもかかわらず、獲得した選挙人の人数では共和党が民主党を上回り、この結果トランプ氏が大統領(1期目)に就任することとなりました。
【問題1】の問2について
正解はエのメキシコです。アメリカ合衆国は18世紀後半の建国以来多くの移民を受け入れてきており、「移民の国」とも呼ばれます。19世紀には、飢饉や貧困といった背景により、アイルランドや中国・インドなどから大量の移民が流入しました。しかし、現在トランプ氏が特に問題視しているのは、アメリカと南部で国境を接するメキシコなど中南米諸国からの不法移民です。アメリカの移民法では、永住権を持つ「移民」として認められるためには移民ビザを申請し、審査を経てビザを取得する必要があります。合法的な移民もいますが、こうした手続きを経ずにアメリカに入国して働く不法移民が急増しており、バイデン政権下の2021~2024年には合計730万人に及んだとされています。これらの人々は、アメリカの経済成長率を押し上げる一方で、若者から職を奪うなどの懸念を受けて社会問題となっています。トランプ氏は前回大統領に当選した際にもこれらの不法移民を問題視し、メキシコとの国境沿いに壁(いわゆるトランプの壁)の建設を始めました。
【問題1】の問3について
正解はイです。消去法で考えるとよいでしょう。アについて、地図で青く塗られた19州は、北東部や西海岸に多く位置しています。共和党を赤で、民主党を青で表すことは、2000年の大統領選挙の頃から定着した慣習で、現在では大統領・上院の多数派・下院の多数派を共和党がすべて独占することを「トリプル・レッド」などと言ったりします。
ウが正しいことは、アメリカ合衆国の初代大統領がジョージ・ワシントンであることを知っており、地図の北西端にワシントン州を見つけられれば判断できます。なお、東部に位置するアメリカの首都もワシントンD.C.と呼ばれますが、ここは正式には「コロンビア特別区」(District of Columbia)といい、どの州にも属さない連邦政府の直轄地です。
イに関して、アメリカの二大政党については「共和党は農村部、民主党は都市部で強い」という傾向が知られています(参考:読売新聞オンライン2024年1月15日付「基礎からわかるアメリカ大統領選挙」)。実際に2020年の人口統計に基づく全50州(ワシントンD.C.を除く)の人口密度と、今回の選挙における両党の選挙人団の獲得結果との関係を調べてみると、人口密度が高い25州では民主党獲得州:共和党獲得州の比が13:12となるのに対して、低い25州では6:19となり、大きな違いがあることが分かります。
【問題2】の問1について
「2の1億3627万9841乗の一の位」をいきなり調べるのは難しいので、まずは小さい数から調べていきます。以下では、「aのb乗」を「a^b」と表します。
まず、2^1=2なので、2^1の一の位は2になります。次に2^2=4なので、2^2の一の位は4となります。これを繰り返していくと
2^3=8より一の位は8
2^4=16より一の位は6
2^5=32より一の位は2
2^6=64より一の位は4
であることが分かります。
このことから、2^nの一の位は「2→4→8→6→2→4→8→6→…」と、4種類の数字が繰り返し現れている(周期4で繰り返されている)ことが分かります。したがって、2^nの一の位は、nを4で割った余りが何になるかで分類することができます。すなわち、nを4で割った余りが1ならば一の位は2、2ならば4、3ならば8、0(4で割り切れる)ならば6となります。
136279841を4で割った余りは、136279841=4×34069960+1より1となります。したがって、2^136279841の一の位は、2^1の一の位と同じ2となるので、2^136279841-1の一の位は1であることが分かります。
一般に、同じ自然数を複数回かけた数において、一の位には周期性が見られます。本問のような周期性に関する問題では、自分でいくつかの数について「実験」してみることでどのような周期になっているかを見抜くことが大事になります。
なお、100=25×4より、136279841の百の位以上の部分(136279800)は4で割り切れます。そのため、136279841を4で割った余りを考えるには、下2桁の41を4で割った余りを考えればよいです。
【問題2】の問2について
大きな素数を発見するには、それが素数であるかどうかを確認するために膨大な計算が必要となります。それを1台のコンピュータで行うと非常に時間がかかるため、複数のコンピュータをネットワークでつなげ、それぞれのコンピュータで分担して計算させることで計算時間を短縮する手法がよく使われます。このような手法を「分散コンピューティング」といい、この手法を使って行われているプロジェクトとして、記事にあった「大きな素数を見つけるプロジェクト」の他に「タンパク質の構造を調べるプロジェクト」や「新型コロナウイルスを解析し、ウイルスに有効な物質を探すプロジェクト」などがあります。
分散コンピューティングでは、世界中の複数のコンピュータをつなげてデータをやり取りする必要があります。そのためには、データのやり取りについて、コンピュータの性能や製造したメーカーなどに依存しない統一的なルール(規約)を定める必要があり、これを「プロトコル」といいます。代表的なプロトコルとして、インターネット通信で使われる「TCP/IP」、ウェブページの閲覧で使われる「HTTP」、メールの転送で使われる「SMTP」などがあります。
プロトコルを統一することにより、スーパーコンピュータだけでなく、世界中にある家庭用のパソコンや、スマートフォンなどとも通信を行うことができます。今回の記事にあった大きな素数を見つけるプロジェクト(GIMPS)でも、登録さえすれば、皆さんの家にあるパソコンを使ってこのプロジェクトに協力することができます。
その他の選択肢の意味は以下の通りです。
プロセッサ…コンピュータ内で計算処理を行う装置の総称で、特にCPUがよく知られています。
プロバイダ…インターネットの接続サービスを提供する事業者のこと。
プロローグ…物語の冒頭や導入部を意味する言葉で、情報通信とはあまり関係ありません。
【問題2】の問3について
下線部③で、メルセンヌ素数は「2を複数回かけた数から1を引いた形の素数」であると書かれています。この定義を基に、2をかける回数を増やしていきながら、素数になるかどうかを調べていきましょう。
2を1回かけてから1を引いた数は2^1-1=1であり、これは素数ではありません。
2を2回かけてから1を引いた数は2^2-1=3であり、これは素数なので、一番小さいメルセンヌ素数は3です。
2を3回かけてから1を引いた数は2^3-1=7であり、これは素数なので、2番目に小さいメルセンヌ素数は7です。
2を4回かけてから1を引いた数は2^4-1=15であり、15=3×5と素因数分解できるので、素数ではありません。
2を5回かけてから1を引いた数は2^5-1=31であり、これは素数なので、3番目に小さいメルセンヌ素数は31です。それ以降は127(=2^7-1)、8191(=2^13-1)、131071(=2^17-1)と続いていきます。
