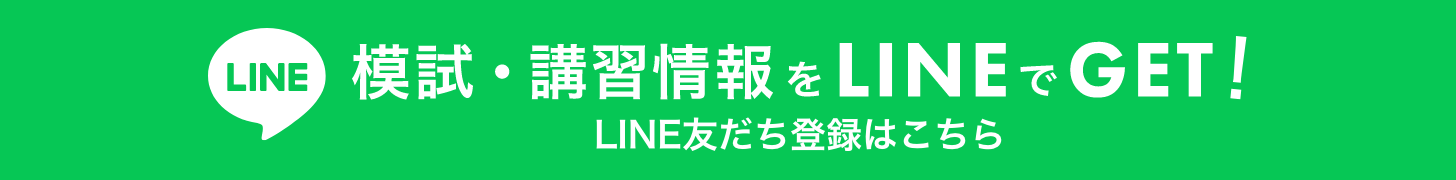受験勉強は、長い時間机に向かえば成果が出るものではありません。
- ・どれだけ深く集中できたか
- ・どれだけ無駄なく進められたか
- ・どれだけ疲れをためずに継続できたか
など、同じ1時間の勉強でも知識の定着や実践力の習得は大きく変わります。
本記事では、受験生が直面しがちな「集中が続かない」「計画どおりに進まない」「長時間の勉強で疲れがたまる」という悩みを解決する勉強グッズとその“使い方”を解説します。
目的に合った道具を上手に使い、勉強環境を整えて勉強の質を底上げしていきましょう。
便利な勉強グッズのメリット

2つの核心「環境の最適化」と「行動のトリガー化」
勉強グッズの最大の価値は、「環境の最適化」と「行動のトリガー化」にあります。
環境の最適化とは、雑音や眩しさ、姿勢の崩れなど集中を妨げる要因を取り除き、集中の立ち上がりと持続を助ける環境を整えることです。一方、行動のトリガー化は、「耳栓をつけたら勉強開始」「ホワイトノイズを流したら英単語を覚える」といった“スイッチ”を日常に設計し、勉強を始めることへの心理的ハードルを下げることです。
なお、グッズは高価・多機能である必要はありません。毎日同じ手順で使え、設定に迷わず、すぐ始められる—そんな“シンプルさ”が大きな成果につながります。
集中力の向上—小さなストレスを減らす
話し声や生活音、暗さや眩しさ、姿勢の不安定さといった“小さなストレス”で集中力はすぐに低下してしまいます。雑音を抑え、視界と姿勢を安定させるだけで、同じ勉強内容でも理解の深さや記憶の定着、処理スピードが目に見えて変わります。
まずは、音・光・姿勢の三要素から最も気になるものを集中的に整えましょう。
例えば“音”なら、勉強を始めるたびに耳栓か環境音アプリのどちらかを必ず使うと決めるだけでも集中力の向上につながります。
効率的な時間管理—見える化と時間ブロック
時間管理のポイントは、タスクの見える化と時間のブロック化です。することを目に見える形にし、あらかじめ時間の枠を決めて取り組むことで、先延ばしが減り、優先順位に迷う時間も短縮されます。
時間の枠が決まると目の前の勉強に集中できます。
例えば、午前は「数学50分×2」、午後は「英語長文40分×2」、夜は「復習30分×2」のように時間ブロックを決めておくと、計画と実績のズレが小さくなり、1日のリズムが安定します。
ストレス軽減—体と心の負担を同時に減らす
長時間の勉強を継続するには、身体的ストレス(眼精疲労、腰痛など)と精神的ストレス(達成感不足、焦燥感など)を同時に和らげることが重要です。適切な照明やチェアクッションで身体の負担を減らし、進捗の見える化や小さな達成の積み重ねで心の負担を軽減すると、長時間集中して勉強することができます。
目安として、45~60分に一度は立ち上がって肩回しをしましょう。勉強するときの姿勢は足裏を床に接地し、肘は机面とほぼ水平を意識すると、翌日に疲れを持ち越しにくくなります。
勉強がはかどる勉強グッズ11選

ここからは、受験生の悩みを「集中力」「時間管理」「ストレス軽減」の3つの観点に分けて、それぞれに効くアイテムと具体的な使い方を紹介します。重要なのは、“一度に全部”ではなく、“今の課題に直結するひとつ”から始めることです。
まずは、アイテムを1つだけ使い、1週間効果を実感してから次を試してみましょう。この順序が、最短で効果に到達するコツです。
集中力アップを助けるグッズ
まずは、音や光、姿勢の面から集中を支える道具を紹介します。“没入空間”を、手元に小さく作っていきます。
耳栓
耳栓は、周囲の話し声や生活音が気になって集中が途切れやすい人におすすめする道具です。思考の立ち上がりが格段に早くなります。
遮音性能は製品ごとに異なり、パッケージに記載されたNRR(米国規格)やSNR(欧州規格)の数値が目安になります。数値が高いほど遮音が強い一方で、長時間の装着で圧迫感を覚える場合もあるため、フォーム型(スポンジ状で膨らむタイプ)とフランジ型(傘のような形状)の双方を試し、自分の耳に合うものを選ぶのがポイントです。
使い方のコツは、勉強開始の“合図”として装着し、ポモドーロなどの短い休憩ごとに一度外して耳を休めることです。
最初の数日は圧迫感を覚える人もいますが、装着の角度や挿入の深さを微調整すると、違和感は大きく減ります。人の声を完全に遮断する必要はありません。大切なのは、気が散る音を遮断して、思考の流れを保つことです。
ホワイトノイズマシン
耳栓が合わない、あるいはタイピング音や人の話し声が気になるという人には、ホワイトノイズマシンが有効です。
一定の音(ホワイト、ピンク、ブラウンなど音色のバリエーションがあります)を流すことで、環境音をやさしくマスキングし、注意の焦点が外れにくくなります。音色によって体感は大きく異なり、高音寄りのホワイトノイズは明るく、低音寄りのブラウンノイズは包み込むような感触があります。
最初は音量を控えめに設定し、人の会話がかすかに分かる程度から始めると違和感が少なくなります。勉強の科目を切り替える時に音色を変えると、環境がスイッチの役割を果たし、気持ちの切り替えがスムーズになります。
夜間や静かな図書室では音量に配慮し、必要であればイヤホン型のノイズ生成アプリを併用するなど、周囲への配慮と自分の集中の両立を心がけましょう。
目に優しいデスクライト
夜に勉強することの多い人や夕方以降に目がしょぼしょぼして能率が下がる人には、デスクライトの見直しが効果的です。参考書やノートを使って勉強するときは、十分な照度とムラの少ない配光が確保されているほど、眼精疲労が軽減され、細かな文字や図形の読み取りが快適になります。
暗記科目ではやや照度を高めて集中モードに切り替え、記述や復習ではやや暖色寄りに調整して、刺激を抑えた落ち着きある環境にするなど、タスクに応じた“光のプリセット”を持つと、後半の目の疲れがぐっと軽くなります。
関連記事:自宅で集中できる環境づくり-デスクライトを適切に使用しよう!
ブックレスト(読書スタンド)
「参考書が閉じてしまう」「机に伏せるように読んで首が痛い」といった悩みには、ブックレストが効果的です。ページを押さえたまま適切な角度で固定できるため、視線が安定し、首や肩の負担が減少します。
A4対応で角度調整ができ、ページ押さえがしっかりしたものを選ぶと厚い問題集でも快適に使えます。
使う際は、参考書を正面やや低めに立て、ノートは水平に置いて視線移動の距離を最短化します。これだけで、要点抽出や転記、図の写し取りがスムーズになり、勉強の質も上がります。いろいろな教科で使えるため、机上の“標準装備”にする価値の高いアイテムです。
時間管理をサポートするグッズ
集中の基盤が整ったら、次は「何を・いつ・どれくらい」するのかを可視化し、先延ばしを防ぐ仕組みを整えます。ポイントは、しっかりと計画を立て、迷いを減らすことです。
タイマー付きスタディプランナー
「計画と実績がズレてしまう」「気づけば時間切れになっている」という人には、タイマー機能と日・週単位の記録欄が一体化したスタディプランナーが有効です。
選ぶときは、1日の流れと1週間の全体像を同時に俯瞰できるレイアウトで、自分の文字サイズに合う記入欄を備え、カウントダウンが一目で分かるような見やすいものを意識しましょう。
使い方は簡単で、朝のうちに「本日の優先タスク(3件)」を決め、各タスクに時間の枠を割り当てます。勉強が終わったら、実績と差分、そして気づきを2~3行だけ書き留めます。これを繰り返すと、だんだんと時間見積もりの精度が上がり、同じ内容でも「どれくらい時間がかかるのか」という肌感覚が育ってきます。
- ■運用のルールは明快に
- ・記入は1回2分以内に終える
- ・長文は書かない
- ・週末に見開きで振り返って翌週の配分を微調整する
これだけで継続のハードルが下がります。今日から始めるなら、今この瞬間に「本日の優先タスク(3件)」を書き、最初のタスクだけでも時間を割り当ててタイマーをスタートしてみてください。小さな始まりが、その日の流れをつくります。
関連記事:勉強を効率化する時間を無駄にしないための5つのテクニック
ホワイト(コルク)ボード
タスクが多いほど、頭の中だけで整理しようとすると混乱してしまいます。
A3以上のホワイトボードやコルクボードを座ったときに自然と視界に入る位置へ設置し、視線の動線に沿って情報を配置すると、迷いが減り、次の一手が速くなります。
上段には今週のゴールを短く書いて旗印にし、左列には「本日の優先タスク」を3件だけ大きくはっきりと記します。右列には保留や後回しの項目をまとめて置き、下段は完了ログとして、終わったものを消したり外したりするための領域にします。
運用のポイントは、マグネットや付箋を使って柔軟に入れ替えられるようにすること。そして発色の良いマーカーで一目で読める大きさに書くことです。
朝5分で「本日の優先タスク(3件)」を決め、夜5分で残タスクを翌日に送る。この10分だけで、時間の使い方が上手くなります。
ストレス軽減に役立つグッズ
集中と時間管理を支え続けるには、体と心の負担を軽減することが不可欠です。痛みや疲れを我慢して勉強を続けても、勉強の効率は下がるばかり。早めの対策が、いちばんの近道です。
チェアクッション
長時間座って勉強する受験生にとって、腰や坐骨への負担は天敵です。高反発やジェルタイプのチェアクッションは、圧を分散し、骨盤が立ちやすい座位を助けてくれます。座面が安定し、通気性が確保され、滑り止めで位置がズレにくいものを選ぶと、長時間でも快適です。
座るときは、骨盤をやや前傾させて背骨を自然に伸ばし、足裏をしっかり床につけて、膝が90度前後になるよう整えましょう。肘は机とほぼ水平に保ち、肩をすくめない姿勢を意識すると、首や肩の負担も軽くなります。さらに、45~60分ごとに一度立ち上がって肩や股関節を軽く回し、血流を促すと、集中を持続できます。
痛みやしびれが続く場合は使用を中止し、必要に応じて医療機関に相談してください。
関連記事:正しい姿勢と座り方で学習しよう!
インクリメンタル暗記カード
インクリメンタル(少しずつ増やしながら反復する)な暗記カードは、覚えたものと曖昧なものを分けて復習間隔を調整するのに最適です。
紙のリングカードであれば、色分けやタブで段階を分け、理解度に応じてカードを入れ替えます。アプリ型であれば、復習タイミングを自動で提示してくれる間隔反復機能を活用すると便利です。
大切なのは、覚えたカードの復習間隔は長くし、曖昧なカードは間隔を短くする“正直な仕分け”を徹底すること。進捗が目に見えると達成感が得られ、モチベーションの維持にもつながります。語彙や用語、年号の暗記と相性が良く、通学時間や隙間時間にも取り入れやすいのが強みです。
1セッションは10~15分を目安にするのがおすすめです。
関連記事:脳科学に基づく暗記のコツ!学生が知っておくべき8つのテクニック
ホットアイマスク
目の疲れや肩こりが出ると、注意力は急降下します。約40度に温まるホットアイマスクは、短時間で目の周囲の血行を促し、眼精疲労を和らげます。使い捨てタイプは手軽さが魅力で、USBタイプは繰り返し使えてタイマー機能が便利です。
ポモドーロを2~3セット終えたタイミングで、10分だけ目を温めると、視界のクリアさが戻り、次のセットも集中が続きやすくなります。椅子に座ったまま使い、タイマーで区切って寝落ちを防ぎましょう。
熱さを感じにくい状況では低温やけどに注意し、温度や時間は無理のない範囲で調整しましょう。
関連記事:勉強の合間にリラックスできる方法とアイテムをご紹介
良質な文房具
意外と効果を発揮するのが、筆記具やノートの書き心地の改善です。滑らかな低粘度ボールペンやゲルインク、消しやすい消しゴム、紙質の良い方眼罫ノートを選ぶだけで、勉強のモチベーションが上がります。
強調色は2色までに絞り、たとえば「赤=定義」、「青=例や注意点」といったルールを統一すると、ノートが“後で役立つ”構造になります。
新しい文房具のお試しは月1回など頻度を決めましょう。まずは今使うペンを1本「主力」に決め、ノート冒頭に色ルールを書き込んでから勉強を始めると、迷いが減って手が動きやすくなります。
初期セットアップガイド:今日からできる導入手順

今日から実践できるように予算帯ごとに必要最低限のセットアップから始めましょう。
まずは「取りかかりの手軽さ」と「集中の継続」を最小の投資で実現します。
0円で今日からできる初期設定(通知オフと環境音アプリの活用)
最初は0円でできる対策から。スマホに勉強専用のフォーカスモードを作り、通知をオフにして不要なアプリをブロックします。タイマーはホーム画面からワンタップで起動できるようにし、勉強開始の合図にしましょう。同時に、紙のToDoリストに「今日の最優先3つ」を手書きで固定します。
環境音アプリでホワイトノイズやブラウンノイズを小音量で流すと、外部の雑音を穏やかにマスキングできて、集中力を高められます。勉強を始めるときは「フォーカスON→タイマー開始→ToDoリストを机の中央へ」の順を毎回同じにするのもポイントです。
〜3,000円で整える即効セット(学習スイッチですばやく集中)
予算が3,000円までなら、耳栓と学習タイマー、書き心地の良いボールペンをそろえます。耳栓はフォーム型やフランジ型を試し、自分の耳に合う遮音レベルを選びます。タイマーは静音・ワンタッチ・ダイヤル型を使って、スマホの誘惑から距離をとりましょう。ペンは低粘度またはゲルインクの細字を1本「主力」と決め、ノートの冒頭に色ルール(例:赤=定義、青=例や注意)を書き込んでから始めると、迷いなく書けます。
開始の合図は「耳栓→タイマー→開始」と3動作に固定しましょう。
〜10,000円で長時間に強い環境へ(目と首の負担を軽減)
1万円程度までなら、デスクライトかブックレストのどちらかを追加して、長時間の負担を軽くします。デスクライトは演色性が高く、ちらつきの少ないものを選び、利き手と反対側から紙面を斜めに照らすのが基本です。ブックレストはA4対応で角度調整ができ、ページ押さえが強いものだと、首の前傾が減って視線移動もスムーズになります。
デスク全体の配置は、紙面までの視線距離をおよそ30~40センチに保ちましょう。ホワイトボードを使用する場合は正面から少し見上げる位置に置くと、自然と視界に入り、タスクを意識しやすくなります。
1日のリズムを固定する(ルーティンを決める)
1日のリズムをあらかじめ決めておくと迷いなく勉強できます。
朝は5分で「今日の3優先」を確定し、午前・午後・夜の3~4ブロックに勉強を割り当てます。昼に5分だけ計画を見直してブロックを再配分し、夜は実績と差分、気づきを2~3行で記録して締めます。
こうした計画の時間は合計15分以内に収め、勉強そのものにエネルギーを使うことが原則です。毎回の開始手順(フォーカスON→タイマー→耳栓→開始)を決めておくことで、条件反射のように集中に入れるようになります。
目的別ミニ診断(自分に合うアイテムを30秒でチェック!)
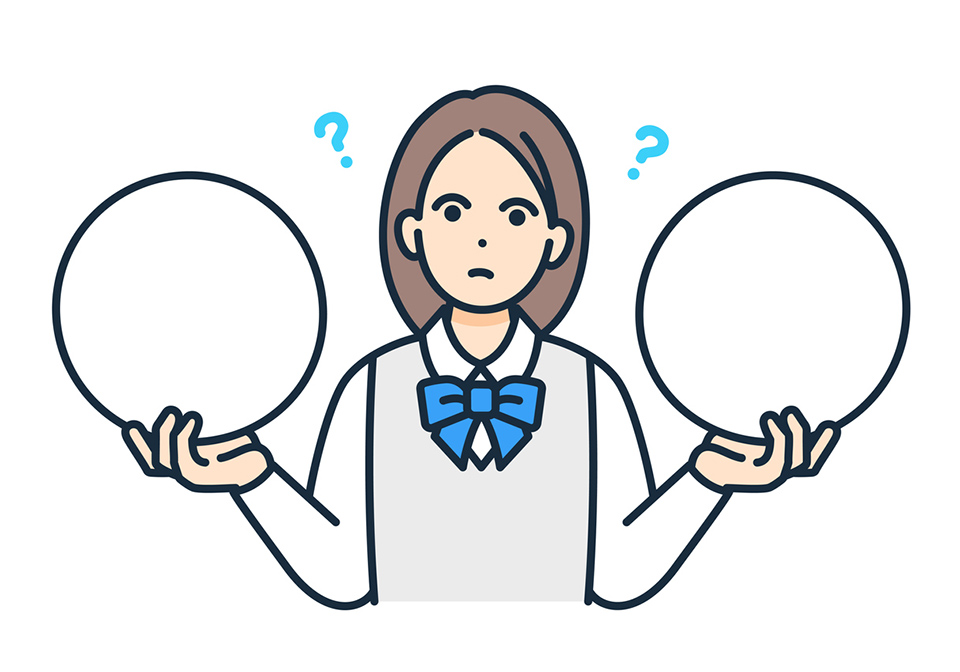
どれから始めるか迷う場合は、簡単な自己診断で絞り込みましょう。
- 1.音が気になる(雑音で集中が切れる)
- おすすめ:耳栓/ホワイトノイズ
効果:外部刺激を減らして集中力の低下を防ぐ - 2.時間が溶ける(取りかかりが遅い・気づくと時間が過ぎる)
- おすすめ:ポモドーロ/タイマー
効果:開始の合図を固定し、すぐに始められる - 3.体がつらい(目・首・腰が痛く集中が続かない)
- おすすめ:デスクライト/チェアクッション
効果:勉強環境を整えて長時間の勉強でもペース維持 - 4.計画が崩れる(計画どおりに進まない)
- おすすめ:スタディプランナー+ホワイトボード
効果:予定・実績・振り返りを可視化して軌道修正を容易に
選び方とルールが大切!
- ・1つに決める:上記から最も当てはまるカテゴリを1つ選ぶ
- ・1週間試す:同じ条件で使い続け、手応えを確認
- ・必要なら増やしてみる:効果が限定的なら、別のカテゴリから1つ追加
何から始めたらいいか迷うときは診断の結果で一つに決め、1週間使ってみて手応えがあるか確認し、必要なら次の一つを増やしていく。この“少しずつ積む”姿勢が、最小のコストで最大の成果につながります。
よくある失敗と対策
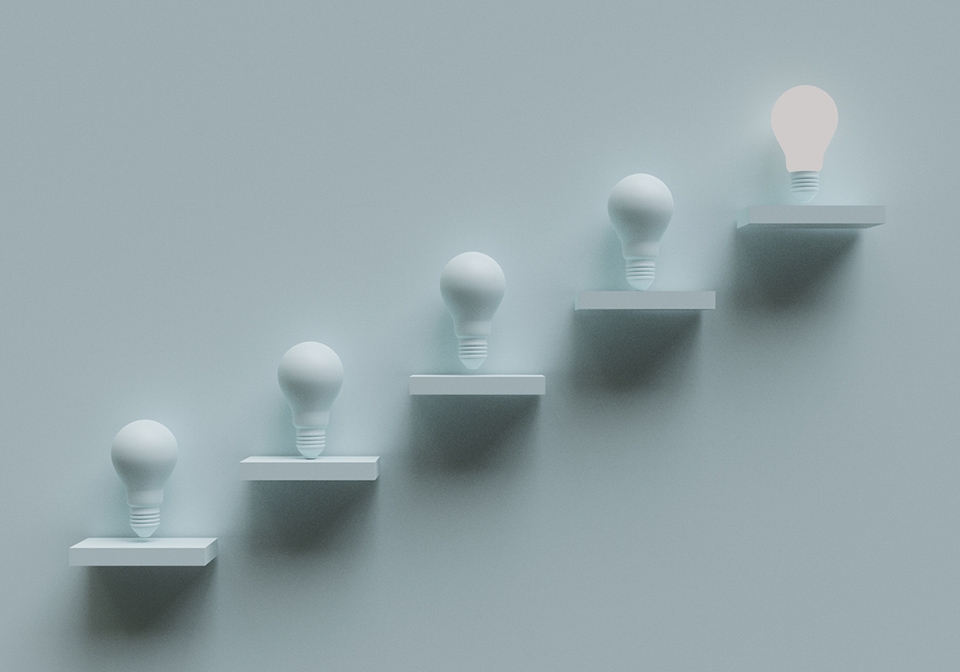
勉強グッズは、購入しただけで満足してしまい、使わずに終わるケースが少なくありません。「買って満足→未使用」を避けるには、まず購入後の1週間は使用するようにしましょう。
開始時刻、使った道具、勉強内容、ひと言の感想だけをメモし、日曜日に5分で見返す。これだけで、自分に合った設定やタイミングが見えてきます。また、高機能な道具ほど設定が複雑で、十分に活用できず負担になることがあります。最低限の機能だけ使って始めて、週1回だけ設定を見直し、不要な機能はオフにする方針で進めましょう。
まとめ
勉強の効率は、「環境 × 仕組み × 負担軽減」で底上げできます。
まずは自分に合うもの一つから小さく始め、週に1回だけ設定と配置を5~10分見直すだけで、1~2週間後には“変化”を感じられるはずです。
すべてを一度にそろえる必要はありません。今の自分の課題に一番近い道具を一つ選び、1週間使い切る。それが、志望校合格に向けた最短の積み上げになります。
Tweet