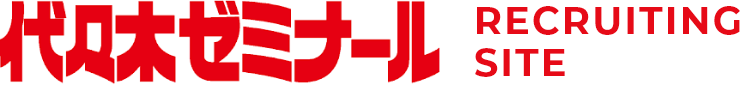新入職員座談会
2024年入職の皆さんに
代ゼミや業務について、話してもらいました!

大阪南校
営業推進室

国際教育センター
学務室

本部校代ゼミタワー
授業運営管理部 教務室高校生コース
代ゼミを選んだきっかけ
H.M:自身が受験生のときに、周囲に気軽に相談できる相手がいなくて、精神的にきつかったんです。なので自分みたいな生徒が気軽に頼れるような存在になりたいと思っていました。大学では教職課程を取っていたので教育実習にも行きましたが、そのときに忙しい学校現場のなかで生徒一人ひとりを見るって結構大変だなと感じました。代ゼミの説明会に参加したときに「親身の指導」という言葉を聞いて、ここだったら自分のやりたいことができるかもと思いましたし、学校以外の教育現場でじっくり生徒を見ることができる環境に惹かれました。
Y.Y: 大学は教育学部に通っていて、元々私立学校の先生になりたいと思っていました。ただ私立の先生は非正規の雇用が多かったので、途中から教員ではなく一般企業への就職活動に切り替えました。 いろんな業界を見ていたときに参加した代ゼミの説明会で、副理事長が「大学受験は認知能力や知識だけではなく、それ以外の部分も伸ばすもの。」というお話をしていました。実際自分も同じように考えていたので、興味を持って代ゼミを受けたのが始まりです。教育業界は代ゼミしか受けていなかったです。
T.K:大学では文学を学んでいたので文章を書く新聞記者か、塾講師をしていた経験から教育業界に進むかで悩んでいるときに、代ゼミの説明会がたまたま大学で実施されていました。私自身、浪人生のときに代ゼミへ通っていて、ある程度どんな仕事ができるのかイメージがついていたのと実際に働いてみたいと思ったので代ゼミを選びました。
今の業務について

Y.Y:高校生コースの職員全員が共通して行っている業務は、生徒対応と案内書の校正、講座の申し込み手続きがあります。僕は高1~高3まで幅広い学年の担任をもっています。加えて個人の業務として、テキストや欠席者用の模試の管理、映像授業の受講ブースの管理、イベントや保護者面談の実施、体験入会用のコンテンツをホームページに掲載する依頼など幅広く行っています。
H.M:国際教育センターでは、帰国生の大学入試を専門的にサポートしています。私は生徒対応がメインで、大学に提出する志望理由書の添削や試験前の面談練習をしています。志望理由書を添削するときは、生徒とたくさん話をしてどのようなことを考えているかを聴きながら作成を進めていきます。生徒対応以外では、年末に来年度のチラシ作成を任せていただいて、仕事の幅が広がったと感じ、とても新鮮で楽しかったです。また、外国に住んでいる方とオンライン面談をして疑問点の解消やアドバイスをしたり、直接来校した方の対応も徐々にできるようになってきました。
T.K:僕は学校営業と模試運営業務とクラス担任の3つの業務を中心に行っています。営業では代ゼミに通う生徒の出身高校を訪問して、生徒の近況報告を行っています。また、模試や進学講演の実施など、外部だからこそ得られるものを提供することで、生徒や学校全体が伸びるきっかけになるような提案をしています。模試運営では問題の準備からアルバイトの手配、前日の準備や展示物の作成、ホームページに掲載する記事の作成をしています。先輩や上司にも信頼していただいて、大阪南校での模試運営に関わるほとんどの仕事を任せてもらっています。クラス担任では地方の国公立を目指す生徒向けのコースを担当していて、ホームルームや面談などで生徒や保護者の方とお話ししたり、面接や小論文の添削も行っています。
配属されてからの日々を振り返って
Y.Y:タワー校に配属されてから1か月間は、校舎内のいろいろな部署を周り、基本業務を習いました。そのなかでも申込システムを覚えることが特に難しくて、慣れるのに数ヶ月かかりました。教わってからすぐに申し込み対応をしないといけなかったので、結構大変でした。高校生コースの申し込みは特に複雑で、最初のうちは何が何だか分からないものが多かったです。
H.M:国際教育センターでは、授業開講に合わせて6月末くらいに生徒が入ってくるので、配属後すぐに生徒対応をする機会が多くありました。生徒対応の合間を縫って入試や大学について勉強しなければいけないので、体感としてはすごくバタバタしていました。9月頃から試験が始まるので、配属された6月~10月くらいまで怒涛の忙しさでしたが、先輩職員がサポートしてくれたので、とても心強かったです。
T.K:新入職員研修のときに本部校でOJTを経験したので、配属校舎に行く前から何となく仕事のイメージがついていました。実際に大阪南校でさまざまな部署の仕事を経験すると、校舎独自の業務や全員で校舎運営を行うなど、イメージと違うことがあったので驚きの連続でしたね。予想外のことがたくさんあったので、それに対処していく日々でした。
やりがいに感じたこと
H.M:やりがいを感じた瞬間は、やっぱり合格発表の報告のときでした。生徒が今まで頑張ってきた努力が実った瞬間に立ち会えることは、とても素敵なことだと思うし、普段生活しているなかで人の夢が叶う瞬間に出会うこともなかなかないと思うので、それに立ち会えるのはこの仕事の特権だなと感じました。逆に辛い経験を共有することも大事だと思っていて、辛い経験から生徒が人として成長していく姿を間近で見て、“自分ももっと頑張らないと”と背中を押してもらっているところもあります。そういう風に仕事に向き合えるのもやりがいであり、特権だと思います。

Y.Y:ある保護者の方から教育情報について聞かれた際、少し手が空いていたのでたくさん調べて、パワーポイントを作って2時間くらいプレゼンしたことがあるんですよ。そしたら終わった後にとても感謝してくださって、出願する大学が決まった際にも報告しに来てくれました。生徒が合格するかは分からないですが、その人の人生の一部に関わることができたことにやりがいを感じました。
T.K:先月高校に営業へ行った際、模試の申込書を持っていったら、先生から「まさに今回頼もうと思っていたものを持ってきてくれて嬉しい」と言葉をいただきました。それがとても嬉しくて、単純なので営業めっちゃ楽しい!と思いました。そのときは、模試もほとんど終わっていた時期で資料として持っていけるものが限られていたんですが、とにかく何か持っていかないことには話す材料もないと思って、少し先に実施予定の模試を提案するために持っていきました。すごく喜んでくださったので、嬉しかった思い出の一つです。
大変だったこと
H.M:生徒によってはやる気に差があり、こちらがどれだけサポートしようとしても、校舎に来てくれないことには何もできないので、それがもどかしいです。自分が掛ける言葉がうまく伝わっているのか、その人の心に響いているのか、やる気に繋がっているのかが全然分からないような生徒もいるので、どう対応するかというのはしばらく悩みました。声掛けをすることもモチベーションを保つうえで大切だと分かってはいるのですが、まだ難しくてそれが結構大変でした。また、ただでさえ変化が激しい教育業界ですが、帰国生入試は私自身が未経験ということもあって、次々に分からないことが出てくるので、情報を集めて自分のなかで整理して理解する、という作業にとても苦労しましたし、今でも苦労しています。
Y.Y:何かやるたびに絶対一つ躓く。一番大変だったのは、イベントのパワーポイント資料を作成したときです。元々のデータを大きく変えた方が良いのではないかという話になり、自分のなかでいろいろと考えたのですが、何が良くて、何が悪いのかということがあまり分からず、それを判断することができなかったです。イベントでは先輩が僕の作った資料で講演したのですが、客観的に見てとても微妙な資料だったなと思いました。紙で見たときは結構良い資料ができたと思っていたのですが、実際に講演で聴くと分かりにくいデータを選んでいたり、強調したいところを何度も繰り返し伝えるような内容になっていました。たくさん時間を使って情報を調べたり、構成も考えたりしましたが、いまいちな出来だったので悔しくもあり、印象にも残っています。
T.K:3つあって…高校営業に初めて一人で行った際にタイミングが悪く、期末テスト期間中に行ってしまったんですね。先生が忙しそうにしているなかで、自分の伝えたい内容が伝えきれないまま10分くらいで終わってしまって、何をしに来たんだろうと反省しました。あとは、クラス担任業務で小論文の問題を丸々作問したことあって、それがすごく大変でした。講義動画を探して、問題も過去問に寄せて作成をして、生徒さんにも解いてもらいましたが、難易度として適切でないものが出来上がってしまったみたいで、少し挫折しました。3つ目が完全な失敗談なのですが、ホームページに限定公開で載せないといけないものを誰でも閲覧できるように掲載してしまったことがあり、担当者の方に謝罪しに行くという大変な経験をしました。本来は失敗する前に確認ができていれば問題は起きなかったことなので、自分自身のダブルチェックに対する意識が変わるきっかけになり、その意味では良い経験ができたと思います。

新入職員研修について
Y.Y:最初の1週間は東京エリアに配属の職員も学生寮に宿泊したので、慣れない環境で特に辛かったです。研修でやって良かったのはメールの作り方、電話応対、パソコン研修ですね。メールもたくさんやり取りしますし、電話も結構かかってくる部署なので役立っています。 もちろん研修で全部の知識を身に付けたというわけではないですが、配属後に0から始めるよりは、「そういえば研修でやったな」って思い出しながらできた分、スムーズに業務にあたることができた場面が多かったです。
H.M: 印象に残っているのはグループワークですね。大学生のときもグループワークはしましたが、気心知れた相手とすることが多かったので、社会人としてまだあまり関係性ができていない人と一つのものを作り上げる難しさを感じました。性格とか、これまでの環境も全く違うので意見もいろいろ出て面白かったし、その分大変さもあって印象に残っています。 あとは、4月の半ば頃にお散歩研修があったんですけど、指定されたスポットを回りつつ、それ以外は自由だったのでグループでランチのお店を決めたりとか、同期との会話も弾んで楽しかったです。
T.K:私は地方校舎に配属のため、研修期間の2か月間学生寮で過ごしていました。Y.Yくんは寮生活しんどかったと言っていましたが、僕の場合は学生時代夜型だったので研修中に完全に朝型に切り替えられて良かったです。OJT研修で行った部署は、今の業務と関わりのある部署なので連絡することもあって、OJTで職員の顔と名前や部署の雰囲気を知っていた分やりとりしやすかったです。 他に校舎研修として新潟校に行きましたが、本部校と地方校舎って雰囲気も違うので、大阪の校舎で働くにあたって先に地方校舎の雰囲気を経験できたのは良かったなと感じます。

部署の雰囲気
T.K:先生方と話す機会が多いこともあってか、明るくて話し上手な先輩が多いです。皆さんとても気に掛けてくれて嬉しいです。営業推進室は、校舎のなかでも特に明るい方が多く雰囲気が良いですし、部署内でしっかり情報共有がされているので、働きやすいと日々感じています。
H.M:先輩に質問をしたら親身に聞いてくれたり、それ以上の情報も教えてくれたりして優しい方が多いです。この1年で質問が山ほどあるなかで聞きやすい環境に本当に助けられました。しっかり自分のスタイルを確立して仕事をしている方が多いので尊敬できるし、すごく働きやすい職場だと感じます。
Y.Y:代ゼミの職員は皆さん優しいですよね。午前中1人で勤務のときもあるので、分からないときに他部署の先輩に聞くことが多かったです。新入職員研修のOJTでお世話になった他部署の先輩に助けてもらうこともあって、入職してからの一回一回の出会いがとても大きいと感じました。
同期との関係について
H.M:同じ部署に配属された同期の存在は大きいですね。スタートが一緒ということもあって、同期の働く姿を見て頑張ろうと思える部分がありますし、お互いに一番聞きやすい関係ではあると思うので、頼りになるし、切磋琢磨できる良い関係だと思います。
Y.Y:僕も同じ部署に同期がいるのでH.Mさんの気持ちが分かります。学ばせてもらうことも多かったり、自分のできていないことが分かって焦ったり、勝手に良い刺激をもらっています。テキストの発注で他部署の同期とやり取りすることもあります。
T.K:同じ大阪南校に配属された同期はフロアが違うこともあり、仕事上であまり関わることはないですが、この間本部校の職員が大阪南校に来た際に、その職員の後輩にあたる同期の話で盛り上がりました。いろいろな校舎や部署に同期がいるので、今まで関わりがなかった職員との話のネタにできるのはとても心強いですね。
仕事とプライベートの両立
Y.Y:土日に生徒対応や模試などのイベントが入るので、出勤することも多いですが、大学生のときより遊びや旅行に行くことが多くなった気がします。友達と会うと不安な気持ちをリフレッシュできるので、11月は週1で遊んでいました。海外サッカーを見ることも好きなのですが、夜遅い時間に放送されるのでサッカー観戦と仕事の両立はできなくなりました(笑)
H.M:私は基本的にインドアなので、家に帰ったらドラマや映画を見てダラダラ過ごすことが多いです。休日は友達と会って息抜きすることもあります。2年目は気持ちの余裕も出てくると思うので、脱インドアを目指して旅行などプライベートでのインプットを増やしていきたいと思っています。代ゼミは、業務に支障がなければ休暇が取りやすい環境なので、自分の趣味に時間を費やせることが魅力の一つだと思います。
T.K:私も基本的には家にいることが多いですが、模試で休日出勤が多く、平日休みになったりするので、買い物や食事に行っても人が少ない中でできることが助かっているというか、自分には合っていると感じます。最近は、休みの日に整体へ行ったりして身体のメンテナンスをしています。デスクワークが多いので、腰が痛くて…朝はラジオ体操もやっています!
今後やりたいこと
T.K:1年目は先輩方から教えてもらうことが多く、学びの一年だったと思います。2年目になると、知っていて当然ということも増えると思うので、今年教えてもらったことを応用しながらより改善して、業務を効率化して貢献できるようになりたいです。同時に若手職員としての意見を求められることがあるので、フレッシュな意見を出せるようにしたいと思います。
Y.Y:1年目は自分のことで精一杯すぎて、周りの状況を全然把握できずに終わってしまいました。若手として意見を求められることもあったので、2年目からはもう少し周りを見られるようになりたいと思っています。また、自分が困っていたときに先輩から声を掛けてもらったり、助けてもらうことが多かったので、意識的に周りに配り声を掛けられるようになりたいです。
H.M:生徒にとって自分が頼れる存在だったか少し自信がないので、来年は入試や生徒のことなど情報収集をよりしっかり行って、担任として最適な勉強環境を生徒に提供していきたいです。また、生徒の状況や求めるサポートは人によって違うと思うので、生徒それぞれに合わせた提案ができる担任になることを目標にしています。帰国生は親元を離れて受験勉強に挑む方が多いので、勉強以外の不安や障壁がないような環境づくりをしたいと思っています。

就活生へのアドバイス

H.M:私は、早くから業界を絞りすぎて3年生の秋頃まで教育業界のなかでどう働こうかを悩み続けてしまった時間があり、インターンシップに行けませんでした。今仕事をしていて、学生時代にもっと幅広く経験して、いろんな気付きを得ていたら良かったと思うことがあります。 興味がある業界でも違うなと思うことはあるだろうし、逆に興味がないと思っていたら自分に合う仕事が発見できるとか、インターンシップはそういう気付きの時間になると思うので行けば良かったかなと後悔してますね。

Y.Y:さっきH.Mさんは業界を絞りすぎたと言っていましたが、僕は逆に興味のある分野を広げすぎてしまって、だんだん自分でも何がしたいのか分からなくなったときがあったんです。就活を始めた頃にはインターンシップは終わっていて、経験や知識がないのでどんなことが自分に合っているのかよく分からない状態で就活を進めている感じでした。 インターンシップでは業界ごとの経験ができるので、経験していればある程度絞れたと思いますが、それができないのが大変でしたね。大変だと思うけどインターンシップに参加して、ある程度自分の興味の範囲を理解しておくのは大事かなと思います。

T.K:僕は大学での学びをさらに研究したいと思い、大学院に進むことを考えていました。所属していたゼミは、大学3年生の頃から卒論を書き始めていたのですが、なかなかうまくいかず、3年生の2月頃に院進をあきらめて就活に切り替えました。院進をやめて就活を始めたときに、説明会で情報収集をすると意外な発見もあり、興味がない業界でも説明会を聞くと意外と自分は志望度が高いんじゃないかという会社と出会ったりもしました。そういう経験も何回かしたので、まずは何かしら行動を起こしてみる!ということは大事なんじゃないかなと思います。
この座談会は2025年1月に行ったものです。