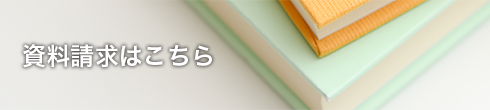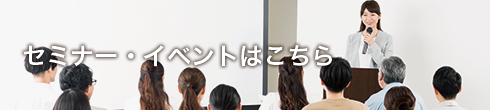夏の勉強法のポイント②
夏の勉強法のポイント①
2020.08.05

もうすぐ夏がやってきます。
高3生の皆さんにとっては、夏休みの間にどれだけ大学合格に必要な基礎力を確立できるかが受験の成否を決めると言っても過言ではありません。
高1・高2生の皆さんも、目標を定め計画的に学習を進めることが大切です。
1学期中は学校行事や部活に追われてなかなか思いどおりに学習が進まなかったという人、そろそろ具体的な志望校に的を絞った対策をスタートさせたいと思っている人など様々だとは思いますが、高校生の皆さんにとってはまとまった学習時間が取れる貴重な機会です。
今のうちから夏の学習計画を考えておきましょう。
- ※本記事の内容は、新型コロナウイルス感染症による影響は考慮されておりません。ご了承ください。
まずはスケジュールを作成しましょう
長期にわたる夏休み期間中、効率的に学習し成果をあげるためには、綿密なスケジュールの作成が必要不可欠となります。
その際のポイントは次の3つです。
①実行可能な、余裕のあるものを作成する
実行不可能なものは論外ですが、「余裕のない計画」も「実行不可能な計画」と変わりありません。体調を崩すことや急な用事が入ることもあると思います。
そういった諸事情による遅れを取り戻す余裕がまったくない計画だと、計画と実際とのズレが大きくなる一方で、計画を立てる意味がありません。
計画を立てる際は「調整日」を組み込んでおくことをおすすめします。②夏期講習会や模試を活用し、バランスの取れたスケジュールを作成する
「ひたすら自習で乗り切る」というのは計画のコントロールが難しく、一般的に精神力を要します。
また、偏った学習に陥る危険もありますので、夏期講習会や公開模試を受けて、学習のリズムや内容に変化をつけるようにしましょう。
「次の模試では○○大学の合格判定B以上をとる」というように具体的な目標を設定すれば、モチベーションを高めることができます。③生活のリズムを崩さないよう、午前中を活用し、学習時間帯を固定する
夏の間に朝寝坊の癖をつけてしまうと大変です。なかなかその癖が直せず、2学期が始まっても夜型の不規則な生活リズムをひきずってしまう人が毎年少なからず見受けられます。
1学期中と同じ時刻に起きて、朝食を必ず摂り、午前中にしっかり学習する習慣をつけておきましょう。
1学期の復習を徹底的に
現役生にとって夏期における学習の大きな柱は1学期の復習です。
この夏に納得のいく復習ができれば、その自信を踏み台に2学期でのステップアップにつなげることができます。
①やるべきことに優先順位をつける
課題を明確にし、それをひとつひとつこなしていけば、学力は必ず伸びていきます。まずはやるべきことをすべてリストアップし、それらに学習の優先順位をつけましょう。
例えば英語であれば「苦手な構文と文法を克服すべくテキストの問題をやり直す」、数学であれば「授業では理解していたはずなのに自力では解けない問題をまとめる」など、何を使って、何を行うかを具体的にすることが大切です。②1学期の授業用ノートを大いに活用する
ノートには追加事項を盛り込んで完成させ、繰り返し覚え込み、知識の定着を図りましょう。
③覚える「作業」を目で確認するだけで終わらせない
「書くこと」を面倒がらずに、積極的に手を動かしましょう。
さらに、英語や古文・漢文は音読して文章のリズムに慣れましょう。この方が確実に記憶に残ります。④独力での復習が困難と思われる内容や分野は、積極的に夏期講習会を活用する
苦手な科目・分野については、独学より授業を受ける方が効率的です。
また、誤解や勘違いを訂正する意味でも、夏期講習会は大いに活用すべきです。⑤1学期に受験した模試は、間違えた問題や解けなかった問題を中心に解き直し、さらに模試専用の復習ノートを作る
代ゼミJOURNAL「模試の活用法①」「模試の活用法②」で説明したとおりです。
1学期中にこれができなかった人は、夏休み中に実践しましょう。
可能なら志望校対策も
夏期講習会などで志望校の過去問を研究することが大変有効です。
もちろん、独学で「過去問」を解くという方法もありますが、よほど実力のある人以外は、夏休みのうちからの過去問「研究」は難しいでしょう。
解法のポイントや出題傾向について、多くの大学入試を研究している先生の授業を受けるのが、過去問研究のスタートとしては確実で効率的です。
いつから過去問対策を始めればいいのか分からない人も多いようですが、それは学習の進み具合によって異なります。
「1学期の学習内容に積み残しはない」という人は、夏の初めから志望校の過去問に触れたり、出題内容やレベルの大まかな傾向を研究したりして、その方向性や今後の学習方針を立てるようにしてみるとよいでしょう。
しかし、「まだ自信のない科目や分野がいくつもある」という人は、焦りは禁物です。
過去問研究以前に、「基礎固め」に力を入れ、弱点や苦手を克服していきましょう。
過去問研究開始は夏休み明けからでも遅すぎるということはありません。
「夏休み明けからは絶対に過去問研究を始めるぞ」という意気込みで基礎固めに励んでください。
なお、過去問研究は全科目同時にスタートさせる必要はなく、準備のできた科目からで構いません。
夏に学習すべきことは?①
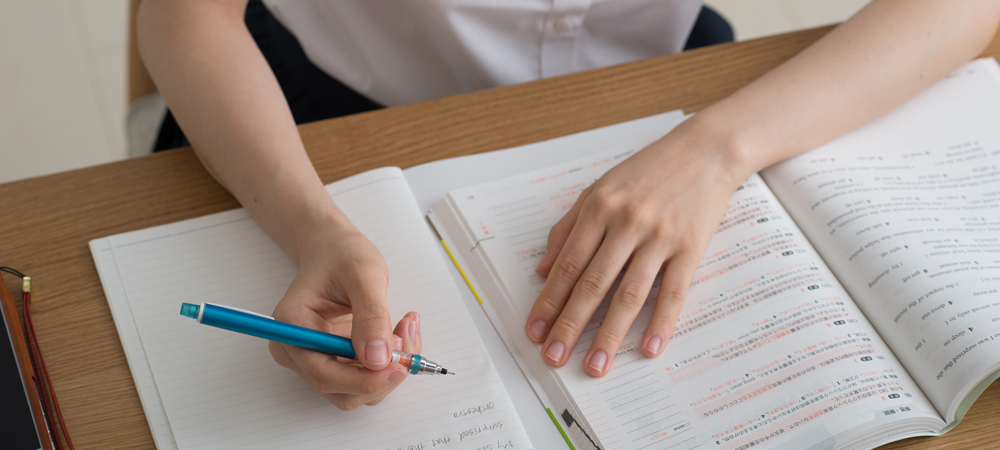
夏は合格に必要な基礎力をしっかり確立する大事な期間です。1学期中は手つかずだった科目、不安な科目や弱点分野は、特に集中的な対策が必要となります。
今の自分に必要なものをしっかりと把握した上で有効な学習プランを組むようにしてください。
不得意科目・苦手分野の克服
苦手科目・分野はできるだけ早い時期に克服しておかなければなりません。
入試結果から見ると、全科目まんべんなく得点できた人が合格している傾向は明らかです。
したがって、苦手克服は夏の最優先課題となりますが、苦手な科目・分野を自分ひとりの力で克服するのは簡単ではありません。
苦手科目がなくなると他の教科・科目にも好影響を与えることが多いことも考えると、まずは苦手科目・分野を中心に学習することをおすすめします。主要科目の学力アップ
主要科目(文系の英・国、理系の英・数)は入試での配点が高いことが多いため、その学力をアップすることができれば、入試本番で大いに有利になります。
しかし、主要科目はどれも暗記主体の科目ではないため、すぐに力が伸びるというものではありません。
したがって、主要科目については、苦手分野があればそれを克服するよう学習し、それ以外の分野では新しい問題に接することによって実戦力を高めることがポイントです。全科目まんべんなく
ある程度得点できる科目でも、長い間学習せずにいると学力は落ちていくものです。
知識を忘れてしまうということもありますが、問題を解く要領やコツを忘れてしまうことも大きな原因の一つです。
「夏の重点科目とは考えていないから」と考えて、その科目をまったく学習しないまま夏を終えてしまい、結果として大きく成績を下げてしまう危険性があります。
重点科目以外でも、他の科目とのバランスをとることを意識するとよいでしょう。
夏に学習すべきことは?②
理科や地歴公民の未習分野・単元
理科や地歴公民の未習分野・単元に夏の間に触れることは非常に有効です。
高校の授業の進度によっては未習のまま終わってしまう分野・単元もあるようですが、そうでなくても履修が高3生の終わりに近い頃になってしまう分野・単元は当然あります。
そのような項目はどうしても時間不足や演習不足で、しっかり身につかないものです。
それが入試にあまり出ない項目であれば大きな問題はありませんが、入試で頻出する項目であった場合、入試が目前に迫った時期まで全く学習しないというのでは、大変なことになります。
そこで、夏期講習会などで未習分野・単元を扱う講座を受講し、その内容の概略を把握するとともに、入試でよく問われるポイントや、解答作成のプロセスに少しでも慣れておくことをおすすめします。
そうしておけば、秋以降にもう一度その分野・単元の授業を受ける時には、とてもスムーズに頭に入って来るでしょうし、独学でもかなりのことがこなせるようになるでしょう。志望校対策
前述のとおり、「志望校対策の前にまず基礎固め」なのですが、「基礎がある程度できた」という人は、ぜひそれぞれの大学入試に直結した演習を行いましょう。
過去問演習にとどまらず、類題・予想問題を通じて、出題意図や「どのような学力・能力を見たいのか」がわかれば、どういう方向で学力向上を目指せばいいのかが分かるので、さらに心強いはずです。